「投資を始めたいけど、どの商品が安全なのか全くわからない…」
「元本割れだけは絶対に避けたいけど、銀行預金じゃお金は増えないし…」
そんなジレンマを抱えていませんか?
投資の世界には無数の金融商品が溢れており、初心者の方がその中から自分に合った、しかもリスクの低い商品を見つけ出すのは至難の業です。
まず、誠実にお伝えしなければならないのは、「絶対に損しない(元本が保証される)投資商品」は、個人向け国債や定期預金などを除き、基本的には存在しないということです。
しかし、リスクを限りなく低く抑え、長期的に見て損する可能性が低い、いわば「損しにくい」商品は確かに存在します。
この記事では、そんな「損するのが怖い」というあなたのための、具体的な低リスク投資商品を7つ厳選しました。人気の投資信託から、元本保証が魅力の個人向け国債まで、それぞれの商品が「なぜ低リスクなのか」という理由、そして「それでも存在するデメリット」まで、忖度なく徹底解説します。新NISAで買える商品も多数紹介しています。
この記事を読み終えれば、あなたはもう商品選びで迷いません。各商品の特徴を正しく理解し、自信を持って、あなたの資産形成の第一歩にふさわしい相棒を見つけられるはずです。
この記事でわかること
- 「損しにくい商品」を選ぶための3つの大原則
- 初心者におすすめの具体的な低リスク商品7選とその理由
- 各商品のメリットだけでなく、「隠れたリスク」やデメリットもわかる
- あなたのリスク許容度に合った商品の見つけ方がわかる
大前提!「損しない」投資商品を選ぶための3つの鉄則
ここでは、具体的な商品紹介に入る前に、そもそもどのような基準で「損しにくい」商品を選ぶべきか、その判断軸となる3つの鉄則を共有します。この軸さえ持っていれば、将来新しい商品が出てきても、自分で正しく判断できるようになります。
鉄則1:徹底的に「分散」されているか?
投資の基本中の基本は「分散」です。一つの会社の株に全資産を投じるのは、その会社が倒産すれば全てを失うため、非常にハイリスクです。
一方で、投資先が数十、数百と分散されていれば、そのうちの一社が倒産しても全体への影響はごくわずか。これが、損しないための最も重要な考え方です。
鉄則2:長期的にかかる「コスト(手数料)」は低いか?
投資信託などの金融商品には、保有している間ずっと払い続ける「信託報酬」という手数料がかかります。このコストは、あなたのリターンを確実に蝕んでいきます。
例えば、年率1%の信託報酬は、100万円を投資すれば毎年1万円の手数料がかかるということ。リターンが3%出ても、実質は2%になってしまいます。「損しない」ためには、このコストを極限まで低く抑えることが絶対条件です。
鉄則3:自分の「リスク許容度」の範囲内か?
どれだけ優れた商品でも、自分の「リスク許容度(耐えられる損失額)」を超えた値動きをする商品は、あなたにとって「良い商品」ではありません。
暴落時に冷静さを失い、パニックになって売ってしまえば、どんな商品でも損失は確定します。自分が安心して持ち続けられる範囲の商品を選ぶことが、結果的に損をしないための近道なのです。
【王道】インデックスファンド(全世界株式・米国株式)
ここでは、数ある投資商品の中でも、初心者が最初に検討すべき王道の商品「インデックスファンド」について解説します。
インデックスファンドとは?(市場の平均点を狙う投資)
インデックスファンドとは、日経平均株価やアメリカのS&P500といった「株価指数(インデックス)」と同じ値動きを目指す投資信託のことです。特定の指数を構成する数百〜数千の銘柄に自動的に分散投資してくれるため、これ一本で世界経済全体、あるいはアメリカ経済全体の成長に乗ることができます。
なぜ初心者におすすめ?(低コスト・高い分散性・手軽さ)
インデックスファンドが初心者におすすめされる理由は、先ほどの「3つの鉄則」を高いレベルで満たしているからです。
- 高い分散性: 1本で世界中の企業に分散投資できる。
- 低コスト: 信託報酬が年率0.1%台と、極めて安価な商品が多い。(出典: kabutan.jp)※信託報酬は純資産総額などに応じて変動する場合があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。
- 手軽さ: 一度積立設定すれば、あとは自動で買い付けてくれる。
それでも存在する「市場リスク」とは?(暴落時の下落実績)
ただし、インデックスファンドも万能ではありません。市場全体に連動するということは、市場全体が暴落すれば、当然その価値も大きく下落する「市場リスク」を直接的に受けます。
例えば、S&P500に連動するファンドは、2020年のコロナショック時に最大で約-31%も下落しました。(出典: 三井住友トラスト・アセットマネジメント)
具体的な人気ファンド名
こんな人におすすめ!
- 投資の知識はあまりないが、世界経済の成長を信じて長期的に資産を増やしたい人。
- 面倒なことはせず、低コストでほったらかし投資をしたい人。
【安定感】国内債券ファンド
ここでは、株式よりさらにリスクを抑えたい、という方向けの選択肢として「国内債券ファンド」をご紹介します。
債券ファンドとは?(国や企業にお金を貸す投資)
債券とは、国や企業が資金を借り入れるために発行する「借用書」のようなものです。債券ファンドは、主にこの債券に投資をします。満期まで持てば、貸したお金(元本)と利息が返ってくるため、株式に比べて価格の変動が非常に小さいのが特徴です。
なぜ値動きが安定しているのか?
株式は企業の業績によって価格が大きく変動しますが、債券の価値は発行体(国や企業)が破綻しない限り、約束された利息と元本が保証されています。特に、日本国債などを中心に投資する国内債券ファンドは、極めて安全性の高い資産と言えます。(出典: ダイヤモンド・ザイ)
「金利変動リスク」と「インフレリスク」という隠れた弱点
しかし、債券にもリスクはあります。具体的には以下の2つです。
- 金利変動リスク: 世の中の金利が上昇すると、既存の債券の魅力が相対的に下がり、価格が下落するリスク。
- インフレリスク: リターンが低いがゆえに、物価の上昇(インフレ)に負けて、お金の価値が実質的に目減りしてしまうリスク。(出典: 大和アセットマネジメント)
こんな人におすすめ!
- とにかく値動きの大きさが怖い、預金に近い感覚で資産を保有したい人。
- 株式などのリスク資産と組み合わせて、ポートフォリオ全体を安定させたい人。
【おまかせ】バランス型ファンド
ここでは、「資産の配分とか、リバランスとか、考えるのが面倒…」という方のために、すべてを専門家におまかせできるバランス型ファンドを解説します。
バランス型ファンドとは?(資産の幕の内弁当)
バランス型ファンドとは、国内外の株式、債券、REIT(不動産)など、複数の異なる資産を、あらかじめ決められた比率で詰め合わせた、いわば「資産の幕の内弁当」のような商品です。これ1本で、自動的に国際分散投資が実現します。(出典: イオン銀行)
1本で完結する手軽さと自動リバランスの魅力
最大のメリットは、その手軽さです。資産配分の決定から、値上がりした資産を売って値下がりした資産を買い増す「リバランス」まで、すべてを自動で行ってくれます。投資に時間をかけたくない、専門的なことはよくわからない、という方には最適な選択肢です。
信託報酬が割高になる傾向と、その長期的影響
手軽な反面、信託報酬はインデックスファンドに比べて割高に設定されている傾向があります(年率0.2%〜0.8%程度)。このわずかなコスト差が、10年、20年という長期で見ると、無視できないリターンの差となって現れる可能性があります。(出典: Invest-Concierge)
こんな人におすすめ!
- 資産配分などを考えず、とにかく1本で投資を完結させたい人。
- NISAやiDeCoの口座で、完全にほったらかし運用をしたい人。
【分配金】J-REIT(国内不動産投資信託)
ここでは、「値上がり益だけでなく、家賃収入のような定期的な収入も欲しい」という方に向けて、J-REITを解説します。
J-REITとは?(みんなで大家さんになる仕組み)
J-REIT(ジェイリート)とは、多くの投資家から集めた資金で、オフィスビルや商業施設、マンションといった複数の不動産を購入し、その賃料収入や売買益を投資家に分配する商品です。証券取引所に上場しており、株式と同じように手軽に売買できます。
比較的高い分配金利回りが期待できる
J-REITは、利益のほとんどを投資家に分配することで、法人税が実質的に免除される仕組みになっています。そのため、利益が内部に留保されがちな一般企業(株式)に比べ、比較的高い分配金利回りが期待できます。(出典: ACN不動産)
不動産特有の「空室・災害リスク」と金利上昇への弱さ
不動産に投資するということは、当然ながら「空室」や「地震・火災などの災害」といった、不動産特有のリスクを負うことになります。実際に、コロナ禍でホテルの稼働率が下がったり、災害で物流施設がダメージを受けたりして、分配金が一時的に減少した事例も確認されています。また、金利が上昇すると、不動産会社が銀行からお金を借りる際のコストが上がり、収益を圧迫する要因となります。
こんな人におすすめ!
- 株式の値動きとは異なる資産に分散投資したい人。
- 定期的な分配金(インカムゲイン)に魅力を感じる人。
【元本保証】個人向け国債・iDeCoの元本確保型商品
ここでは、「1円たりとも元本を減らしたくない」という、究極の安全志向の方のための最終手段を提示します。
元本確保型商品とは?
文字通り、満期まで保有すれば元本が割れることがないように設計された商品です。代表的なものに、国が発行する「個人向け国債」や、iDeCo(個人型確定拠出年金)の中で選べる「定期預金」「保険」などがあります。
国が保証する究極の安全性と、iDeCoの節税メリット
個人向け国債は、日本国が発行しているため、その信用力は絶大です。また、iDeCoで元本確保型商品を選んだ場合、掛金が全額所得控除の対象となり、高い節税効果を得ながら、安全に資産を積み立てることができます。(出典: ダイヤモンド・ザイ)
インフレに負けるリスクと、利益を逃す「機会損失」
最大のデメリットは、リターンが極めて低いことです。金利が年0.1%にも満たない現在、物価が2%上昇する「インフレ」が起これば、お金の価値は実質的に目減りしてしまいます。これは、元本割れはしていなくても、実質的には資産が減っているのと同じ「インフレ負け」という状態です。また、株式などに投資していれば得られたはずの大きなリターンを逃してしまう「機会損失」も考慮すべき点です。
こんな人におすすめ!
- とにかく元本割れのリスクを一切取りたくない人。
- iDeCoの節税メリットを最大限に活用したいが、値動きのある商品は怖い人。
【比較一覧】あなたに合うのはどれ?7つの商品のリスク・リターン早見表
これまで紹介してきた商品の特徴を一覧にまとめました。ご自身のリスク許容度と照らし合わせながら、最適な商品を見つけてみてください。
7商品の「リスク・リターン・手数料・NISA対応」マトリクス比較表
| 商品タイプ | リスク | リターン | 手数料 | NISA対応 |
|---|---|---|---|---|
| インデックスファンド | 中 | 中〜高 | 低 | ◎ |
| 国内債券ファンド | 低 | 低 | 低 | ◎ |
| バランス型ファンド | 低〜中 | 低〜中 | やや高 | ◎ |
| J-REIT | 中 | 中 | やや高 | ◎ |
| 個人向け国債 | 極低 | 極低 | なし | × |
| iDeCo元本確保型 | 極低 | 極低 | 口座管理手数料 | iDeCo |
あなたのリスク許容度別・おすすめ商品診断チャート
- とにかく安全第一!元本割れは絶対イヤ → 個人向け国債, iDeCo元本確保型
- 預金よりは少し増やしたい。でもリスクは怖い → 国内債券ファンド
- リスクは抑えつつ、ある程度のリターンも欲しい → バランス型ファンド, J-REIT
- 長期的な視点で、世界経済の成長に乗っかりたい → インデックスファンド
損しない投資商品に関するよくある質問(FAQ)
商品選びの際に出てくる、より専門的で細かい疑問に答えます。
- QQ1: インデックスファンドなら、どれを選んでも同じですか?
- A
A1: 似ているようで、細かな違いがあります。特に「信託報酬(コスト)」と「純資産総額(ファンドの規模)」は必ずチェックしましょう。信託報酬は低ければ低いほど良く、純資産総額は大きければ大きいほど、安定した運用が期待できます。
- QQ2: 個人向け国債と銀行の定期預金、どちらがマシですか?
- A
A2: 2025年現在、金利面では大きな差はありません。個人向け国債は半年ごとに金利が見直される「変動金利型」がある点、定期預金は預金保険制度の対象である点などが違いです。どちらも極めて安全ですが、大きなリターンは期待できません。
- QQ3: 「テーマ型ファンド」や「レバレッジ型」はなぜ初心者におすすめしないのですか?
- A
A3: 「テーマ型(例:AI、環境など)」は投資対象が限定的で分散が効かず、一時的なブームで終わる可能性があります。「レバレッジ型」は指数の数倍の値動きを目指すため、当たれば大きいですが、外れた場合の損失も数倍になり、極めてハイリスクです。どちらも初心者にはおすすめできません。
まとめ:『損しない』の本当の意味を理解し、自分に合った商品で賢く始めよう
最後に、この記事の要点を振り返りましょう。
本記事のポイント
「リスクゼロ」より「コントロールできるリスク」を取る勇気
投資において、「損しない」ことの本当の意味は、全く損失を出さないことではありません。それは、自分がコントロールできる範囲のリスクを取り、短期的な値動きに惑わされず、長期的な視点で資産を育てていくことです。
この記事で紹介した商品は、いずれもその手助けとなる、心強いパートナーです。ぜひ、あなたにぴったりの商品を見つけ、賢く、そして着実な資産形成の第一歩を踏み出してください。



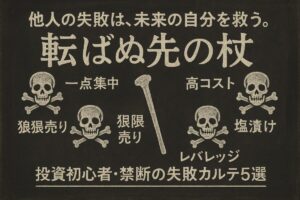
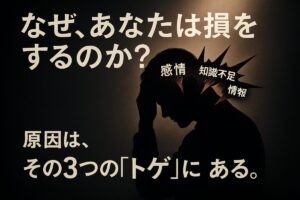
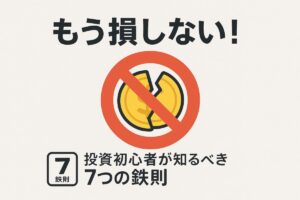
コメント