「新NISAを始めたいけど、銀行と証券会社、一体どっちで口座を開くのが本当にお得なの?」
「安心感なら銀行、手数料の安さならネット証券…と聞くけれど、具体的な違いがよくわからない…」
そんな疑問を抱えていませんか?
ご安心ください。この記事を読めば、手数料、取扱商品、サポート体制、ポイント還元という4つの重要なポイントから、あなたに最適な金融機関がどちらなのか、明確に判断できるようになります。
単なるメリット・デメリットの羅列ではありません。具体的な数値を交えた客観的な比較はもちろん、「なぜ、それでも銀行を選ぶ人がいるのか?」という視点や、SNSでのリアルな評判まで、新NISAの金融機関比較に関するあらゆる情報を網羅しています。
金融庁の最新データや各金融機関の公式サイト情報に基づき、2025年現在の最も正確な情報で、あなたの後悔しない金融機関選びをサポートします。
この記事で、新NISAの銀行比較の全てを理解し、あなたの資産を最大化する最高のパートナーを見つけましょう。
この記事でわかること
- 銀行と証券会社の決定的な違いが数字でわかる
- 手数料で損しないための金融機関の選び方がわかる
- 買える商品の数が全く違うという事実がわかる
- ポイント還元で本当にお得なのはどこかがわかる
- あなたにピッタリな金融機関を診断できる

【結論ファースト】新NISAの比較!銀行と証券会社、あなたにおすすめなのはどっち?
ここでは、詳細な比較に入る前に、いきなり結論からお伝えします。あなたがどちらのタイプに当てはまるか、まずはチェックしてみてください。
【診断チャート】30秒でわかる!あなたにピッタリなのは銀行?証券会社?
いくつかの簡単な質問に答えるだけで、あなたに合った金融機関のタイプがわかります。
銀行がおすすめな人の特徴:投資デビューの不安を解消したい人
診断の結果、「銀行向き」と出たあなたは、コストよりも「安心感」を重視するタイプです。
- 投資の知識に自信がない
- 専門家に直接相談して、納得してから始めたい
- 普段使っている銀行口座とまとめて管理したい
このような方にとって、銀行の対面サポートは非常に心強い味方になります。手数料は割高になる傾向がありますが、それは「安心のための相談料」と割り切れるのであれば、銀行は良い選択肢となるでしょう。(出典: 金融庁)
証券会社がおすすめな人の特徴:コストを抑えて積極的に資産を増やしたい人
「証券会社向き」と出たあなたは、「運用効率」を最優先に考える合理的なタイプです。
特にネット証券は、手数料の安さ、商品の豊富さ、ポイント還元の高さにおいて銀行を圧倒しています。長期的に見れば、その差は大きなリターンとなって返ってくる可能性が高いでしょう。(出典: マネックス証券, SBI証券)
新NISAの比較ポイント①:手数料で見る銀行と証券会社
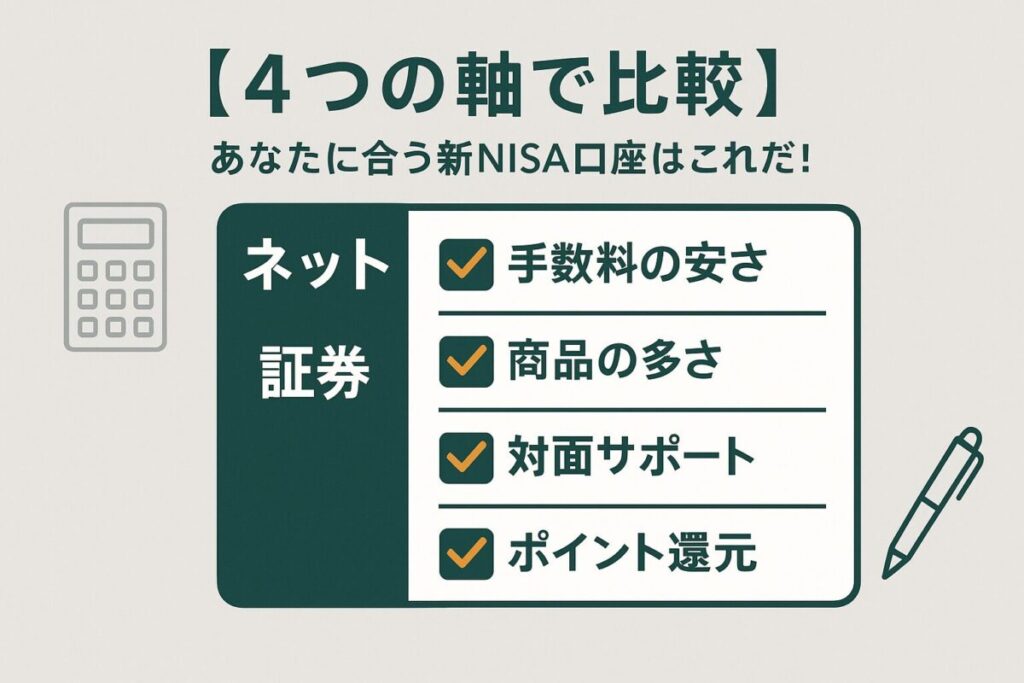
ここでは、金融機関選びで最も重要な要素の一つである「手数料」について、銀行と証券会社を比較します。
一見わずかな差に見えても、長期の資産形成においては大きな違いを生むことを理解しておきましょう。
ネット証券は手数料ゼロが当たり前!銀行との手数料体系の違い
2025年現在、主要なネット証券(SBI証券、楽天証券など)では、新NISA口座におけるほとんどの取引手数料が無料になっています。これは、投資家にとって非常に大きなメリットです。(出典: マネックス証券)
一方で、銀行や対面型の証券会社では、投資信託の購入時に手数料がかかる場合があります。特に、長期的な資産形成でじわじわと効いてくるのが、「信託報酬」という隠れコストです。
【用語解説】信託報酬
投資信託を保有している間、継続的に発生する費用のこと。「年率〇%」のように表示され、投資信託の資産から毎日差し引かれます。
低コストのインデックスファンドでは年率0.1%程度ですが、銀行の窓口で勧められるアクティブファンドなどでは年率1%を超えるものも少なくありません。
【比較表】主要な銀行・ネット証券・対面証券の手数料一覧
| 区分 | 金融機関 | 口座管理料 | 国内株手数料 | 投信購入手数料 | 主力ファンド信託報酬(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行系 | 三菱UFJ銀行 | 無料 | × | 無料〜 | eMAXIS Slim 全世界株式 0.056% |
| 三井住友銀行 | 無料 | × | 無料〜 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックス 0.176% | |
| ネット証券系 | SBI証券 | 無料 | 無料 | 無料 | eMAXIS Slim 全世界株式 0.056% |
| 楽天証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 楽天・全米株式 0.094% | |
| 対面証券系 | 野村證券 | 無料 | 有料 | 一部無料 | ノムラ・フィデリティ日本株基金 1.45%程度 |
長期で響く「信託報酬」の差|人気ファンドで見るコスト比較
例えば、人気のインデックスファンド「eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)」の信託報酬は年率0.056%です。これをネット証券で購入すれば、コストは最小限に抑えられます。
しかし、もし銀行の窓口で信託報酬が年率1.0%のファンドを勧められ、100万円を20年間投資したと仮定すると、運用成果に数十万円以上の差が生まれる可能性があります。
これは、毎年余分なコストが引かれ、その分複利の効果が薄れてしまうためです。(出典: ダイヤモンドZAi)
新NISAの比較ポイント②:取扱商品の数と種類
ここでは、投資の選択肢に直結する「取扱商品」の違いを比較します。手数料以上に、銀行と証券会社では決定的な差があるポイントです。
銀行は「厳選された投資信託のみ」、証券会社は「株式やETFも自由自在」
最も大きな違いは、銀行では株式(個別株)やETF(上場投資信託)を直接購入できないという点です。(出典: 日本経済新聞)
銀行のNISA口座で買えるのは、基本的にその銀行が選んだ投資信託のみ。初心者にとっては「選びやすい」というメリットはありますが、投資の自由度は大きく制限されます。
一方で証券会社、特にネット証券では、数千種類もの投資信託に加え、日本株、米国株、ETF、REIT(不動産投資信託)など、非常に幅広い選択肢から自分の投資戦略に合った商品を選べます。(出典: ダイヤモンドZAi)
【比較表】投資信託の取扱本数は10倍以上の差?
| 金融機関 | 投資信託の取扱本数(目安) |
|---|---|
| 三菱UFJ銀行 | 約400本 |
| 三井住友銀行 | 約350本 |
| SBI証券 | 約1,400本以上 |
| 楽天証券 | 約1,400本以上 |
(出典: つみたてNISAナビ)
このように、選べる投資信託の本数だけでも、ネット証券は銀行を圧倒しています。
米国株や話題のETFに投資したいなら証券会社一択の理由
「AppleやNVIDIAといった米国の成長企業に投資したい」「高配当のETFで分配金生活を目指したい」といった具体的な目標がある場合、選択肢は証券会社一択となります。
銀行のNISA口座ではこれらの金融商品を直接購入することができないため、あなたの投資機会は大きく損なわれてしまいます。
将来的に投資の幅を広げたいと考えているなら、初めから証券会社を選んでおくのが賢明です。
新NISAの比較ポイント③:サポート体制と安心感
ここでは、数字では測れない「サポート」や「安心感」について比較します。特に投資初心者にとっては、手数料以上に重要な判断基準となるかもしれません。
「いつでも窓口で聞ける」銀行の圧倒的な安心感
銀行でNISAを始める最大のメリットは、対面で専門スタッフに相談できる安心感にあります。
「どの商品を選べばいいかわからない」「積立の設定方法が不安」といった疑問を、その場で直接質問し、解決できるのは非常に心強いでしょう。
特に、これまで投資に全く触れてこなかった方や、PC・スマホの操作に不慣れな方にとっては、何物にも代えがたい価値があります。(出典: 金融庁)
ネット証券のサポートは本当に不安?チャット・電話サポートの実態
一方で、ネット証券のサポートはオンラインが基本です。しかし、「サポートが手薄で不安」というのは、もはや過去のイメージかもしれません。
現在では、多くのネット証券がAIチャットボットによる24時間対応に加え、専門スタッフによる有人チャットや電話サポートにも力を入れています。
SBI証券のように、土日でも電話サポートを受け付けているところもあり、利便性は年々向上しています。
【SNSの声】利用者が語るリアルなサポート体験談
銀行の良い評判: 「初めてのNISAで不安だったけど、銀行の窓口で丁寧に教えてもらえて安心して始められた」
銀行の悪い評判: 「相談したら、手数料が高いファンドばかり勧められた気がする…」
ネット証券の良い評判: 「夜中にチャットで質問してもすぐ返事が来て助かった」「SBIの電話サポート、意外とすぐ繋がった」
ネット証券の悪い評判: 「基本的なことはAIチャットで解決するけど、複雑な質問だと電話が繋がりにくい時がある」
このように、どちらにも一長一短があるのが実情です。
新NISAの比較ポイント④:ポイント還元(クレカ積立)のお得度
ここでは、近年新たな比較軸として注目されている「ポイント還元」を比較します。特に毎月コツコツ積み立てる「クレカ積立」では、この差が長期的に大きな違いを生み出します。
【比較表】主要ネット証券のクレカ積立・ポイント還元率
| 証券会社 | 対応カード | 還元率(通常カード) | 貯まるポイント |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 三井住友カード | 0.5% | Vポイント |
| 楽天証券 | 楽天カード | 0.5% | 楽天ポイント |
| マネックス証券 | マネックスカード | 1.1% | マネックスポイント |
| auカブコム証券 | au PAYカード | 1.0% | Pontaポイント |
年間数万円の差も?ポイント還元のシミュレーション
仮に、毎月5万円をクレカ積立するとしましょう。
- 還元率1.0%のネット証券: 年間6,000ポイント(6,000円相当)
- 還元率0.5%のネット証券: 年間3,000ポイント(3,000円相当)
さらに、三井住友カードのプラチナプリファードをSBI証券で利用すれば、期間限定のキャンペーンなどで還元率は5.0%に跳ね上がることも。この場合、年間で最大30,000ポイントもの差がつく可能性があり、これは手数料の差以上にインパクトが大きいと言えるでしょう。(出典: SBI証券)
貯まるポイントの種類と使い道も要チェック
自分が普段貯めているポイント経済圏で証券会社を選ぶのも賢い方法です。
- 楽天経済圏のユーザー → 楽天証券
- Pontaポイントを貯めているユーザー → auカブコム証券
- dポイントユーザー → マネックス証券
- 特定の経済圏に属さないユーザー → Vポイント(旧Tポイント)が貯まるSBI証券
このように、ポイントの使い道まで考えて選ぶと、よりお得に資産運用を始められます。
銀行と証券会社のNISA比較でよくある質問(FAQ)
- QQ1: 銀行でNISAを始めた後、証券会社に移すことはできますか?
- A
A1: はい、年単位での金融機関の変更は可能です。ただし、その年に一度でも取引をすると翌年まで変更できないなど注意点があります。
- QQ2: 結局、投資初心者はどちらから始めるのが安全ですか?
- A
A2: 「絶対に損をしたくない」という気持ちが強いなら、まずは少額から対面で相談できる銀行で始めるのが安心です。慣れてきたらコストの安いネット証券を検討するのが王道です。
- QQ3: 銀行と証券会社で、税金面での違いはありますか?
- A
A3: いいえ、NISA口座内の利益が非課税である点は、どの金融機関で開設しても全く同じです。
- QQ4: 夫が証券会社、妻が銀行でNISA口座を開設することは可能ですか?
- A
A4: はい、可能です。ご夫婦それぞれが、ご自身の判断で金融機関を選ぶことができます。
▼次のステップ:実際に銀行で口座を開設する手順を確認する
手数料やサービス内容を比較し、ご自身に合った金融機関の方向性が見えたら、次はいよいよ具体的な口座開設の手続きです。
こちらの記事では、銀行で新NISA口座を開設する際の詳しい流れや必要書類について、初心者の方にも分かりやすく解説しています。
→ 新NISA口座を銀行で開設する全手順|本人確認から申し込み完了まで解説

まとめ:新NISAの比較は4つの軸で!あなたに最適な金融機関を見つけよう
本記事では、新NISAを始める際の金融機関選びについて、「手数料」「取扱商品」「サポート体制」「ポイント還元」という4つの軸で銀行と証券会社を徹底比較しました。
本記事のポイント
- 手数料: 長期的なコストを考えるなら、各種手数料が無料のネット証券が圧倒的に有利。
- 取扱商品: 投資信託だけでなく、個別株や米国ETFに挑戦したいなら証券会社一択。
- サポート体制: 投資の知識に不安があり、対面での相談を重視するなら銀行に価値がある。
- ポイント還元: クレカ積立などを活用し、お得にポイントを貯めたいならネット証券が最適。
- 利用者比率: 2025年時点で、利用者の約7割は証券会社を選んでいる。
- 結論: 「安心」を最優先するなら銀行、「効率」を最優先するならネット証券がおすすめ。
- 変更は可能: 金融機関は年単位で変更できるので、まずは一歩踏み出すことが重要。
最終的にどちらを選ぶかは、あなたの投資スタイルや価値観次第です。「なんとなく」で選ぶのではなく、この記事で解説したような具体的な比較ポイントを基に、ご自身にとって最適なパートナーを見つけてください。

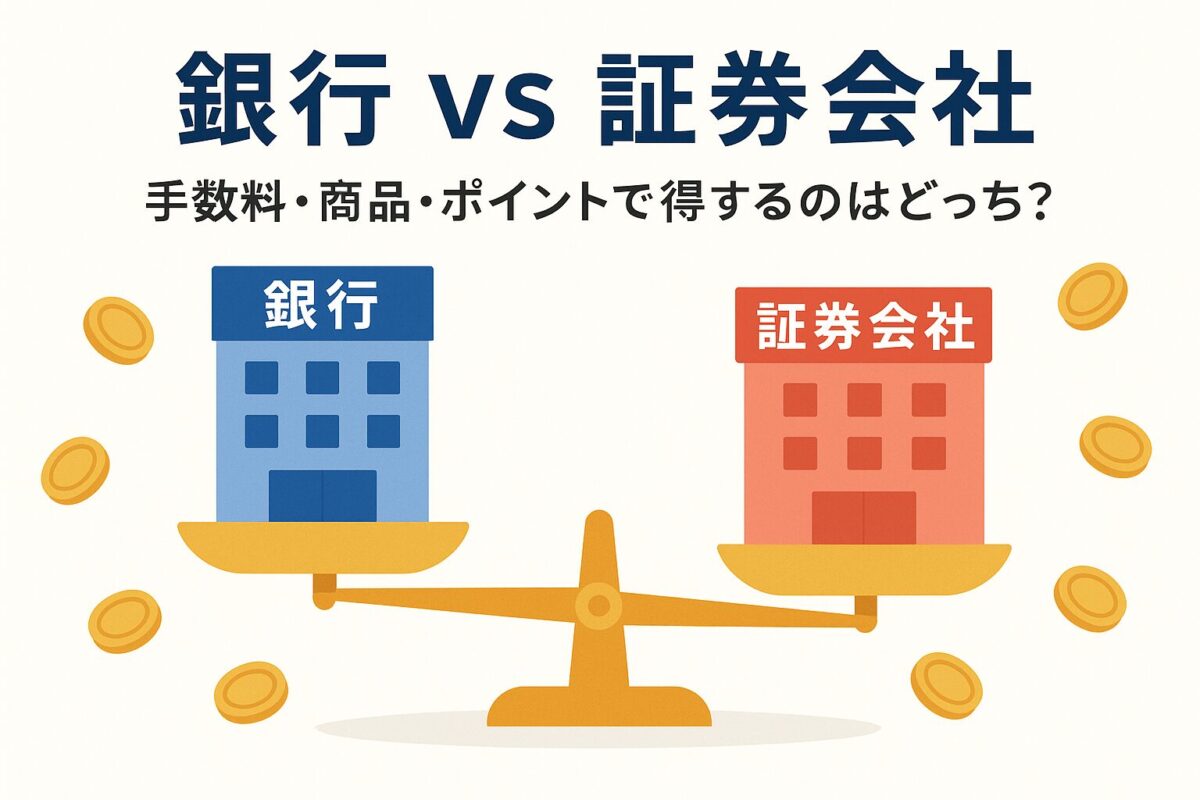








コメント