なぜZ世代は、あの“ちょっと変わった”キャラクター、ラブブにこれほど夢中になるのでしょうか?
その背景には、私たち上の世代とは異なる、彼ら特有の心理と消費行動が隠されています。
この記事では、Z世代のラブブ消費行動を分析し、彼らがモノに求める“感情的な価値”の正体を解き明かします。単なるトレンド解説ではなく、心理学やマーケティングの視点から、Z世代のインサイトを深く理解することができます。
“推し活”や“ぬい活”といったキーワードの深層心理、他のヒットキャラクターとの比較、そして彼らの心を掴む「感情設計」の秘密まで、Z世代の消費行動のすべてを網羅的に解説します。
博報堂若者研究所などの最新の調査データや、大学の研究論文、そしてSNSで語られるZ世代のリアルな声を基に、この現象を客観的に分析します。
この記事でわかること
- Z世代がラブブにハマる、3つの深層心理
- 「推し活」や「ぬい活」の裏にある、自己肯定感と承認欲求のメカニズム
- ちいかわ等、他のヒットキャラとは違うラブブ独自の魅力
- Z世代の心を掴む「感情設計」マーケティングの秘密
- SNSのリアルな投稿から見る、Z世代の新しい消費のカタチ
※この記事では「Z世代の消費行動」に特化してラブブ現象を分析します。そもそも「ラブブはなぜ人気なのか?」その全体像を正確に把握したい方は、まずはこちらの総合解説記事をご覧ください。
→ ラブブはなぜ人気?“感情資本”で読み解くZ世代マーケの最前線
「かわいい」の価値観が変わった?Z世代の新しい美意識
ここでは、ラブブ人気の前提として、Z世代が「かわいい」という言葉に込める意味が、上の世代とは大きく異なっていることを解説します。彼らの新しい美意識を理解することが、ラブブ現象を解き明かす第一歩です。
完璧じゃなくていい:“ぶさカワ”や“クセカワ”が愛される心理
Z世代にとっての「かわいい」は、もはや整った顔立ちや完璧なデザインだけを指す言葉ではありません。彼らは、少し不気味だったり、クセがあったりするデザインに“ぶさカワ”や“クセカワ”といった新しい価値を見出し、熱狂します。(出典: fan.main.jp)
この背景には、「完璧すぎること」や「みんなと同じであること」への疲れがあると考えられます。不完全さやギャップは、むしろ親近感や、他者とは違う「自分だけのもの」という特別感を生み出します。ラブブのニヤリと笑う口元や、ちょっと意地悪そうな表情は、まさにこのZ世代の新しい美意識を体現しているのです。(出典: toyokeizai.net)
「自分だけの特別」を求める心:パーソナライズと自己投影
Z世代は、自分の持ち物に対して「自分らしさ」を表現することを非常に重視します。ラブブのフィギュアに自分でペイントを施したり、服を着せ替えたり、イニシャルチャームを付けたりする「カスタマイズ」文化は、その象徴的な現れです。(出典: accio.com)
彼らは、キャラクターに自分自身を投影し、アイデンティティの一部として取り込みます。ラブブは、その“余白”のあるデザインによって、持ち主が自由に感情を投影し、自分だけの物語を紡ぐことを可能にしています。これは、単なるキャラクターグッズではなく、自己表現のためのキャンバスなのです。
モノ消費からコト消費へ:体験やストーリーを重視する価値観
Z世代の消費は、「モノ」そのものを所有することから、それを通じて得られる「コト(体験)」へと大きくシフトしています。これは消費者庁の消費生活調査などでも指摘されている、現代の大きなトレンドです。(出典: cao.go.jp)
ラブブのブラインドボックスを開ける瞬間のドキドキ感、限定品を手に入れるための抽選に参加する高揚感、そして手に入れたラブブをSNSに投稿し、仲間と共有する喜び。
これら一連の体験こそが、彼らがラブブにお金と時間を費やす最大の動機です。POP MARTは、商品を売っているだけでなく、ファンが参加し、楽しめる「イベント」や「ストーリー」を提供することで、Z世代の心を掴んでいるのです。
なぜ彼らは「推し活」にハマるのか?Z世代の消費行動を分析
ここでは、Z世代の消費行動を語る上で欠かせない「推し活」や「ぬい活」といったキーワードを深掘りします。これらの行動の裏にある心理を理解することで、ラブブがなぜこれほどまでに彼らの心を捉えるのかが見えてきます。
自己肯定感と承認欲求:「推し」は自分を映す鏡
2025年の最新調査によれば、Z世代の約75%が日常的に何らかの「推し活」を行っているとされています。(出典: prtimes.jp)彼らにとって「推し」の存在は、単なる憧れの対象ではありません。推しを応援し、その魅力を語ることは、自分自身の価値観を表現し、自己肯定感を得るための重要な行為なのです。
ラブブを「推す」行為も同様です。自分が選んだラブブを「うちの子が一番かわいい」とSNSで発信し、他者から「いいね」という共感を得ることで、彼らは承認欲求を満たし、コミュニティへの所属意識を高めています。
ラブブは、彼らのアイデンティティを映し出す鏡の役割を果たしているのです。
「#ぬい撮り」413万件の熱狂:SNSでの共感と所属意識
Instagramで「#ぬい撮り」と検索すると、413万件以上もの投稿が見つかります(2025年時点)。(出典: beeats.co.jp)これは、ぬいぐるみを自分の分身やパートナーとして扱い、その日常をSNSで共有する文化が、いかにZ世代に浸透しているかを示しています。
ラブブのファンも、カフェや旅行先など、様々な場所にラブブを連れて行き、その様子を撮影して投稿します。こうした行動を通じて、彼らは同じ趣味を持つ仲間と繋がり、「自分は一人ではない」という所属意識を感じています。
SNSは、彼らにとって単なる情報発信ツールではなく、共感で繋がるための不可欠なコミュニティ空間なのです。
デジタルネイティブが求める「リアルな手触り」の価値
常にスマートフォンを手にし、デジタル世界で多くの時間を過ごすZ世代。しかし、だからこそ彼らは、物理的な「モノ」が持つリアルな手触りや存在感に、特別な価値を見出しています。
ラブブのフィギュアが持つ、ずっしりとした重みや、すべすべとした感触。画面越しでは決して得られないこれらの感覚的な体験が、デジタル疲れした彼らの心に安らぎと幸福感を与えます。ラブブは、リアルとデジタルを繋ぐ、現代ならではの癒やしの存在と言えるでしょう。(出典: note.com)
ラブブのヒットは必然だった?心を掴む「感情設計」の秘密
ここでは、ラブブのヒットの背景にあるマーケティングのフレームワーク、「感情設計」について解説します。この概念を理解することで、ラブブの成功が単なる偶然ではなく、緻密な戦略に基づいた必然であったことが見えてきます。
ドナルド・ノーマンの3つのレベルとは?「感情設計」の基本
「感情設計(Emotional Design)」とは、認知科学者であるドナルド・ノーマンが提唱した、製品やサービスがユーザーに与える感情的な体験を設計するための考え方です。彼は、人間の脳がデザインを処理するプロセスを、「本能レベル」「行動レベル」「反射レベル」の3つのレベルに分けました。(出典: marketingnative.jp)
- 本能レベル: 見た目の美しさや、直感的な「好き・嫌い」といった反応。
- 行動レベル: 使いやすさや、製品を操作する中での達成感や楽しさ。
- 反射レベル: その製品を所有・使用することで得られる自己イメージや、他者との関係性。
優れた製品は、これら3つのレベルすべてにおいて、ユーザーにポジティブな感情を抱かせるように設計されています。
ラブブに適用する:本能、行動、そして“反射”レベルの巧みな設計
ラブブは、この「感情設計」の3つのレベルを見事に満たしています。
このように、ラブブは多層的にユーザーの感情に働きかけることで、一時的なブームでは終わらない、強固なエンゲージメントを構築しているのです。
【比較分析】ちいかわ、おぱんちゅうさぎとの共通点と決定的な違い
近年のヒットキャラクターである「ちいかわ」や「おぱんちゅうさぎ」も、不完全さやギャップを魅力とし、共感を呼ぶという点でラブブと共通しています。彼らもまた、巧みな「感情設計」に基づいたキャラクターと言えるでしょう。
しかし、ラブブが彼らと一線を画すのは、「自己投影のしやすさ」と「リアルな体験との結びつき」の強さです。ラブブは、その“余白”のあるデザインと、着せ替えやカスタマイズといった文化によって、より強く持ち主の「分身」としての役割を担います。
そして、「ぬい活」に象徴されるように、現実世界に連れ出し、体験を共有するパートナーとして、ファンの日常に深く溶け込んでいるのです。
SNSが熱狂を加速させる:UGCがもたらす爆発的拡散力
ここでは、Z世代の消費行動を理解する上で欠かせないSNSの役割について、ラブブの事例を通して具体的に解説します。特に、ファン自身がコンテンツを生み出すUGCの力が、いかにして熱狂を増幅させているのかを見ていきましょう。
「#ラブブのいる生活」:日常を共有する若者たち
InstagramやTikTokで「#ラブブのいる生活」というハッシュタグを検索してみてください。そこには、ファンたちがラブブと共に過ごす、ありふれた、しかし愛情に満ちた日常が溢れています。
カフェのテーブルの片隅に座るラブブ、旅行先の絶景を眺めるラブブ、自宅のベッドで眠るラブブ。これらの投稿は、ラブブが単なるフィギュアではなく、生活を共にするパートナーであることを物語っています。(出典: shibuya109lab.jp)
インフルエンサーよりも強い?ファンによるUGCの信頼性と拡散プロセス
現代のマーケティングにおいて、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の重要性はますます高まっています。企業による広告よりも、友人や同じ趣味を持つ一般のユーザーからの推薦の方が、信頼性が高いと感じるのがZ世代の特徴です。
ラブブのファンが投稿する「開封動画」や「ぬい撮り」は、まさにこのUGCの典型例です。これらのリアルな投稿は、見た人の「自分も欲しい」「仲間に入りたい」という気持ちを自然に喚起し、広告をはるかに超える拡散力を持ちます。
ある調査では、UGCがバズった直後に、関連商品の売上が数倍に跳ね上がったというデータも報告されています。(出典: layers.co.jp)
限定品発売日のSNS:情報拡散が完売を加速させるまで
限定品やコラボ商品の発売日には、SNSが情報戦の舞台となります。公式からの発売告知は、インフルエンサーや熱心なファンによって瞬く間に拡散され、
「どこで買えるか」
「行列は何人いるか」
といったリアルタイムな情報が飛び交います。
このSNSによる情報の高速拡散が、ファンの購買意欲を極限まで高め、発売からわずか数時間での完売という事態を生み出します。「乗り遅れたくない」という焦燥感(FOMO: Fear of Missing Out)を煽るこのプロセス全体が、ラブブの熱狂をさらに加速させているのです。(出典: manamina.valuesccg.com)
専門家はどう見る?Z世代の消費行動に関する考察
ここでは、専門家の客観的な視点を取り入れることで、ラブブ現象をより大きな社会的な文脈の中に位置づけます。社会学者やマーケティングのプロは、この熱狂をどのように分析しているのでしょうか。
社会学者が語る「承認欲求とコミュニティの新しい形」
多くの社会学者は、Z世代の「推し活」を、現代社会における承認欲求とコミュニティの新しい現れとして分析しています。SNSを通じて自分の「好き」を発信し、他者から共感を得ることで、彼らは自己の存在価値を確認し、同じ価値観を持つ仲間との繋がりを実感します。
ラブブのファンコミュニティは、まさにその典型例です。彼らは、ラブブという共通のシンボルを通じて繋がり、お互いを認め合うことで、現実世界とは別の、安全で心地よい居場所を築いているのです。(出典: jsa-net.or.jp)
マーケティングアナリストが分析する「Z世代攻略の鍵」
マーケティングの専門家たちは、ラブブの成功事例から、「Z世代攻略の鍵」を読み解こうとしています。彼らが共通して指摘するのは、「参加」と「共創」の重要性です。
企業が一方的に商品や情報を提供するのではなく、ファンが参加できる「余白」を作り、共にブランドを育てていく。POP MARTのブラインドボックスやカスタマイズ文化は、まさにこの「共創」を促すための巧みな仕掛けと言えます。
これからのZ世代向けマーケティングは、ファンを単なる消費者としてではなく、パートナーとして捉える視点が不可欠となるでしょう。
ラブブコレクターのリアルな声「私たちにとってラブブとは」
専門家の分析も重要ですが、最も説得力を持つのは、やはり当事者であるファンの声でしょう。熱心なコレクターたちに「あなたにとってラブブとは?」と尋ねると、様々な答えが返ってきます。
「単なる癒やし」
「自分を表現するための分身」
「同じ趣味を持つ仲間と繋がるためのパスポート」。
彼らにとってラブブは、もはや単なるフィギュアではありません。それは、自分の人生を豊かにしてくれる、かけがえのないパートナーなのです。(出典: detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
よくある質問:Z世代の消費行動に関するQ&A
ここでは、Z世代の消費行動に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。
- QQ1: Z世代の「推し活」は、昔のアイドルの追っかけと何が違うのですか?
- A
A1: 対象への憧れだけでなく、「推しを応援する自分」をSNSで発信し、他者と共有する点に大きな違いがあります。自己表現やコミュニケーションの手段としての側面が強まっています。
- QQ2: なぜZ世代はそんなにSNSでの「いいね」を気にするのですか?
- A
A2: デジタルネイティブである彼らにとって、SNSは現実世界と同じか、それ以上に重要な自己表現とコミュニケーションの場です。「いいね」の数は、自分の価値や他者からの承認を測る指標の一つとして機能しています。
- QQ3: このような消費行動は、今後どうなっていくと思いますか?
- A
A3: モノの所有欲はさらに減退し、体験や共感、そして自己投資に繋がるような消費がより一層重視されると予測されます。また、リアルとデジタルの境界はさらに曖昧になっていくでしょう。
- QQ4: 企業がZ世代にアプローチする上で、最も重要なことは何ですか?
- A
A4: 一方的に商品を売り込むのではなく、彼らが参加し、自己表現できるような「余白」をブランド側が提供することです。共感できるストーリーや世界観を共有し、ファンと共にブランドを育てていく姿勢が求められます。
まとめ:ラブブ消費行動の分析から見えた、Z世代との向き合い方
本記事では、Z世代のラブブ消費行動を分析することで、彼らの新しい価値観やインサイトに迫ってきました。最後に、そこから見えてきた「Z世代との向き合い方」について、要点をまとめておきましょう。
本記事のポイント
- Z世代の「かわいい」は、不完全さやギャップへの共感を含む。
- 「推し活」は、自己肯定感や承認欲求を満たすための重要な行動である。
- ラブブは、巧みな「感情設計」によってZ世代の心を掴んだ。
- SNSでのUGCは、Z世代の購買行動に絶大な影響力を持つ。
- 他のヒットキャラとの違いは、自己投影のしやすさとリアルな体験との結びつきにある。
- 専門家は、この現象を新しいコミュニティと自己表現の形として分析している。
- Z世代の消費行動を理解する鍵は「共感」「体験」「自己表現」である。
- 企業は、ファンと共にブランドを育てる「共創」の姿勢が求められる。
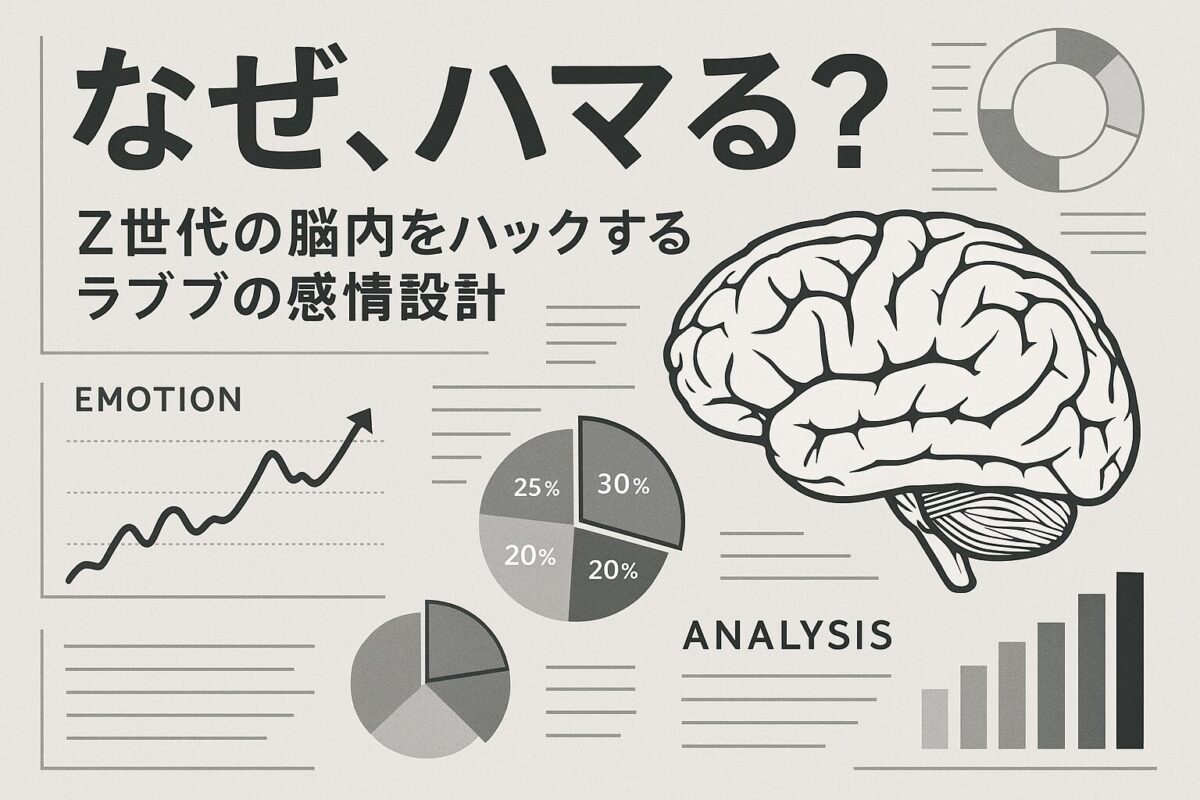



コメント