「税収は過去最高と聞くのに、なぜ現金給付の財源はないの?」
「国の借金って、一体どうなってるの?」
そんな素朴な疑問に、この記事は正面から答えます。
現金給付金の財源がなぜ無いと言われるのか、その本当の理由を、政治と経済の両面から解き明かします。この記事を最後まで読めば、現金給付金が縮小された裏にある「政治の力学」と「経済の思想」という2つの大きな構造が理解でき、ニュースの裏側を読み解く視点が手に入ります。
単に財源の内訳を解説するだけではありません。高市新政権が持ち出した『純債務』という新しいモノサシの意味、公明党離脱が与えた決定的な影響、そして『給付か減税か』という永遠のテーマまで、徹底的に深掘りします。
財務省や日銀の公式データ、そして第一生命経済研究所などの専門機関のレポートに基づき、「現金給付金の財源がなぜないのか」を客観的に分析します。
この記事でわかる「なぜ」の答え
- 理由① 思想の変化: 高市政権が「純債務」を重視し、無制限な赤字国債の発行を抑制する方針に転換したから。
- 理由② 政治の変化: 公明党が離脱したことで、給付金を強く推す声が政権内で弱くなったから。
- 財源の内訳: そもそも3.6兆円の給付金計画は、1.8兆円の財源不足を抱える、元々厳しい計画だったから。
- 代替案の浮上: 「給付付き税額控除」なら、新たな借金をせずに実施できる可能性があるから。
そもそも論:現金給付金の財源3.6兆円の内訳と不足額
ここでは、全ての議論の前提となる「お金」の話を整理します。なぜ現金給付金の計画は、当初から財源確保が難航していたのでしょうか。その構造を数字で見ていくと、問題の本質が浮かび上がってきます。
計画されていた現金給付金3.6兆円の使い道
2025年に検討されていた現金給付金の予算規模は、総額で約3.6兆円と試算されていました。(出典: 日本経済新聞)
これは、全国民に一律2万円を配ることを基本としたもので、非常に大きな規模の経済対策でした。
見込んでいた財源「税収上振れ」とは何か?
政府がこの3.6兆円の主な財源として期待していたのが、「税収の上振れ」です。
用語解説:税収の上振れ
国の予算を組んだ当初の想定よりも、企業の業績好調や消費の拡大などによって、結果的に税金の収入が多くなることです。この「予想外の収入」を、新たな経済対策の財源にすることがあります。
2024年度の決算では、この税収上振れが約1.8兆円見込まれていました。
なぜ足りない?「1.8兆円の穴」が発生した根本原因
ここで問題が浮上します。必要な金額が3.6兆円であるのに対し、財源として計算できるのは1.8兆円のみ。つまり、計画段階で、すでに約1.8兆円もの財源の穴があったのです。(出典: 日本経済新聞)
この不足分を埋めるためには、予備費の活用や、最終的には「赤字国債」を追加で発行する必要がありました。この「新たな借金」の必要性が、後の政策転換の大きな火種となるのです。
理由①:高市政権の「純債務」思想が現金給付金の財源を縛る
ここでは、現金給付金が縮小された最大の理由である「政権の経済思想の変化」を解説します。高市新政権が打ち出した「純債務」という新しいキーワードが、なぜ現金給付の財源にブレーキをかけたのか。そのロジックを紐解きます。
新しいモノサシ「純債務」とは?従来の借金と何が違うのか
2025年10月、高市首相は新たな財政健全化の指標として「政府純債務」を重視する方針を打ち出しました。(出典: 日本経済新聞)
従来の指標である「総債務」が借金の総額だけを見るのに対し、「純債務」は資産も考慮に入れるため、より財政の実態に近いとされています。
用語解説:政府純債務
国や地方が抱える借金の総額(総債務)から、政府が保有している株式や貸付金などの「金融資産」を差し引いた、正味(ネット)の負債額のことです。
なぜ高市政権は「純債務」を重視するのか?その狙いを読み解く
高市政権がこの新しい指標を重視する狙いは、「無制限な赤字国債の発行を抑制する」という強いメッセージを発信することにあります。
「純債務」というモノサシで見ても、日本の財政状況が厳しいことに変わりはありません。この指標を基準とすることで、「これ以上、新たな借金を増やして財政を悪化させるべきではない」という論理を組み立て、大規模な財政出動に対して慎重な姿勢を明確にしたのです。(出典: 日本経済新聞)
この方針転換が「現金給付の財源がない」に直結するロジック
この方針転換は、現金給付金の計画に致命的な影響を与えました。
前述の通り、給付金計画には約1.8兆円の「財源の穴」があり、これは赤字国債の発行で埋めるしかありませんでした。
しかし、高市政権が赤字国債の発行を抑制する方針を明確にしたことで、この穴を埋める手段が失われ、計画そのものの正当性が揺らいでしまったのです。
結果として、現金給付は政策の優先順位を大きく引き下げられ、「財源の確保が困難」という結論に至りました。
専門家の意見:この財政思想は日本経済にプラスか、マイナスか
この財政思想の転換について、専門家の間でも評価は分かれています。
理由②:公明党の離脱が現金給付金の流れをどう変えたか
ここでは、もう一つの重要な理由である「政治力学の変化」を解説します。2025年10月10日の公明党の連立離脱は、単なる政局のニュースではなく、現金給付金の財源を左右する決定的な出来事でした。
連立における公明党の役割とは?「再分配の推進役」だった
連立政権において、公明党は伝統的に国民への直接的な支援や社会保障の充実といった「再分配」を重視する政策を訴え、実現する役割を担ってきました。
特に、現金給付のような政策は、生活者の視点を重視する公明党が強く推進することで、予算が確保されてきた側面があります。
離脱の決定打:財政規律をめぐる自民党との「思想的対立」
公明党が連立離脱を決めた背景には、この財政に対する「思想的対立」がありました。
国民生活を支援するため、積極的な財政出動を求める公明党と、財政規律を重視し、大規模な支出に慎重な自民党内の主流派との間で、意見の隔たりが埋めがたいものとなったのです。(出典: 日本経済新聞)
結果:政権内で「給付金を推す声」が弱まり、財政規律派が主導権を握る
公明党という「再分配の推進役」が政権内からいなくなったことで、力関係は大きく変化しました。
自民党内の財政規律派の発言力が相対的に強まり、現金給付金のような大型歳出案は、より通りにくい政治状況となったのです。これが、政策が縮小・見直しへと向かった政治的な背景です。
野党に転じた公明党の次の一手は?「給付付き税額控除」での連携
野党となった公明党は、立憲民主党や国民民主党と連携を模索しています。
そして、現金給付に代わる新たな生活支援策として、「給付付き税額控除」の導入を共通の目標として掲げ、協議を進めています。これは、「財源がない」という政府の主張に対抗し、新たな借金に頼らない支援策として注目されています。(出典: 日本経済新聞)
「給付か減税か」現金給付金の財源を巡る永遠のテーマを比較
「財源がないなら、給付ではなく減税をすればいい」という声も多く聞かれます。ここでは、現金給付と減税、それぞれのメリット・デメリットを客観的なデータで比較し、なぜ政府が特定の選択をするのかを考えます。
比較表:経済効果、スピード、公平性で徹底比較
| 現金給付 | 消費減税 | |
|---|---|---|
| 経済効果 | 限定的(貯蓄に回りやすい) | 比較的高い(消費を直接刺激) |
| スピード | 遅い(予算成立・準備に数ヶ月) | 早い(決定すれば即時実施) |
| 公平性 | 所得に関わらず恩恵 | 高所得者ほど恩恵が大きい |
(参考: 第一生命経済研究所)
なぜ専門家は「現金給付は貯蓄に回る」と指摘するのか?
第一生命経済研究所の分析によると、過去の現金給付では、給付額の約2~3割が消費に回らず、貯蓄されたとされています。
これは、将来への不安から、人々が一時的な収入をすぐに使わず、手元に残しておこうとする心理が働くためです。そのため、政府が期待するほどの消費刺激効果が生まれない、と指摘されています。
一方で「消費減税は高所得者優遇」と言われる理由
消費減税は、消費額が大きい人ほど、税金の軽減額も大きくなります。一般的に、高所得者ほど消費額が大きいため、結果として高所得者ほど大きな恩恵を受けることになり、「不公平だ」という批判が出やすいのです。
結論:財源が限られる中で、政府がどちらを選びやすいのか
財源が限られ、かつ「公平性」を重視する現在の政治状況では、全国民が一律に恩恵を受ける「現金給付」や「消費減税」よりも、対象者を絞った「給付付き税額控除」や、特定の層への給付が、より現実的な選択肢として選ばれやすくなっているのです。
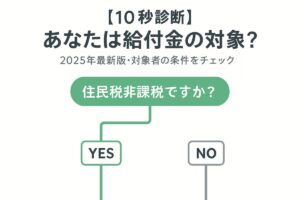
現金給付金の財源に関するよくある質問
ここでは、国の財政に関して多くの人が抱く、素朴で本質的な疑問にお答えします。
- QQ1: 税収は過去最高なのに、なぜ現金給付金の財源がないのですか?
- A
A1: 税収が増えても、高齢化に伴う社会保障費などの支出の伸びがそれを上回っているためです。また、限られた財源を何に使うかは、最終的に政権の政策判断(優先順位)によって決まります。
- QQ2: 「国の借金は国民の資産」だから、もっと国債を発行しても問題ないのでは?
- A
A2: そのような考え方(MMT理論など)もありますが、多くの経済学者や政府・日銀は、国債の大量発行が将来的な金利の上昇や急激な円安を招くリスクを懸念しており、慎重な姿勢を取っています。
- QQ3: 防衛費は増額するのに、なぜ国民への給付は削られるのですか?
- A
A3: それが現在の政権の「政策的な優先順位」だからです。厳しい国際情勢を受け、安全保障への支出を、国民への直接的な経済支援よりも優先度が高いと判断している、と解釈できます。
- QQ4: 結局、財源問題が解決して現金給付が復活する可能性はありますか?
- A
A4: 可能性はゼロではありませんが、高市政権の財政思想や現在の政治状況を考えると、2020年のような大規模な一律給付が復活する可能性は極めて低いでしょう。
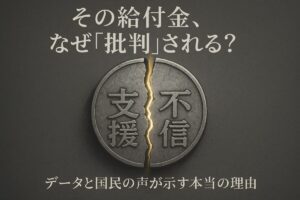
まとめ:現金給付金の財源問題、「なぜ」の答えは思想と政治の変化にあった
本記事のポイント
- 現金給付金の財源問題は、単なる「お金がない」という話ではない
- 思想の変化: 高市政権の「純債務」重視による財政規律強化が最大のブレーキとなった
- 政治の変化: 公明党の離脱により、政権内で「再分配を求める声」が低下した
- 3.6兆円の計画には、元々1.8兆円の財源の穴が存在していた
- 代替案「給付付き税額控除」は、新たな借金をせずに実施できるため、政治的に浮上しやすかった
- 「給付か減税か」の議論は、常に経済効果と公平性のトレードオフの関係にある
- 国民が抱く「財源はあるはず」という感覚と、政府の判断の間には、構造的なギャップが存在する
結論として、「財源がない」という言葉の裏には、政権の経済思想の転換と、連立解消という政治力学の変化という、2つの大きな要因が複雑に絡み合っています。この構造を理解することが、今後のニュースをより深く読み解く鍵となるでしょう。



コメント