「防災グッズを揃えよう」と考えたとき、多くの人が一般的な防災セットを思い浮かべるかもしれません。しかし、地震だけでなく、桜島などの活発な火山と共に暮らす私たち南九州の住民にとって、本当にそれで備えは万全なのでしょうか?
答えは「ノー」です。降灰による健康被害やインフラへの影響も考慮した、「南九州に特化した防災グッズ」の視点が、あなたと家族の安全を守る上で絶対に欠かせません。
この記事では、国が推奨する基本の備えに加え、火山灰対策も網羅した「南九州の住民のための防災グッズ完全ガイド」をお届けします。このチェックリストを片手に、今日から“我が家”の備えを完璧なものにアップデートしましょう。
※この記事では「モノの備え」に特化して解説します。トカラ列島地震の最新状況や、なぜ地震が起きるのかといった全体像は、まずはこちらの総合解説記事をご覧ください。
→【総合解説】トカラ列島地震 最新情報と今後の注意点
まずは基本の備えから。内閣府推奨の「非常持ち出し袋」必須チェックリスト
ここでは、災害対策の基本として、国(内閣府・首相官邸)が推奨する、一次避難(災害発生直後に命を守るために持ち出すもの)のための必須アイテムをチェックリスト形式で紹介します。まずはご自宅の備えが、この基本を満たしているか確認しましょう。
命を守る最低限のアイテム
- [ ] 飲料水:ペットボトルなどで最低1人1日1L。可能なら3Lあると安心。
- [ ] 非常食:調理不要で食べられるもの(カンパン、缶詰、栄養補助食品など)を最低3日分。
- [ ] 医薬品・救急セット:持病の薬、お薬手帳のコピー、絆創膏、消毒液、鎮痛剤など。
情報収集と安全確保のツール
- [ ] 携帯ラジオ:停電時でも情報収集ができる手回し充電式がベスト。
- [ ] 懐中電灯・ヘッドライト:停電時の必需品。ヘッドライトは両手が空くので特に便利。
- [ ] 予備電池・モバイルバッテリー:スマホは今や重要なライフラインです。
- [ ] 軍手・革手袋:ガラスの破片などから手を守ります。
- [ ] マスク:粉塵や感染症対策に。
貴重品と衛生用品
- [ ] 現金:停電時は電子マネーやカードが使えません。小銭も多めに。
- [ ] 身分証明書・保険証のコピー
- [ ] 簡易トイレ・携帯トイレ:断水時に最も困るのがトイレです。
- [ ] ウェットティッシュ・トイレットペーパー
【経験者は語る】基本セットに「これだけは足しておけ!」というアイテム
被災経験者の多くが「本当に助かった」と語るのが、「防臭性能の高いポリ袋」です。生ゴミや汚物処理など、衛生環境を保つために非常に役立ちます。また、「大きめのゴミ袋」も、雨具やシート代わりに使える万能アイテムとして重宝します。100円ショップでも手に入るので、必ず数枚入れておきましょう。
【ここからが本番】南九州の住民が絶対に追加すべき「火山灰対策」グッズ
基本の備えが確認できたら、いよいよ南九州の住民にとって最も重要な「火山灰対策」です。降灰は、単に「汚れる」だけでなく、深刻な健康被害やインフラの麻痺を引き起こします。以下の専用グッズを追加することで、防災レベルを格段にアップさせましょう。
目を守る:粉塵を防ぐ「ゴーグル」は必須
火山灰は、ガラスの破片のように非常に鋭利な粒子です。目に入ると角膜を傷つける危険があるため、目を完全に覆うことができる「ゴーグル」を家族全員分準備しましょう。隙間の多い普通のメガネやサングラスでは不十分です。
呼吸器を守る:普通のマスクではダメ!「防塵マスク(DS2/N95)」の重要性
一般的な不織布マスクでは、細かい火山灰の粒子を防ぎきれません。吸引すると気管支炎や喘息悪化の原因となるため、国家検定に合格した「DS2」や「N95」規格の防塵マスクを備えておくことが極めて重要です。
体を守る:灰を吸着させない「レインコート」と「長靴」
火山灰は衣類に付着しやすく、家の中に持ち込んでしまうと清掃が大変です。外出時には、表面がツルツルしていて灰を払い落としやすいレインコートやウインドブレーカーを着用するのがおすすめです。また、地面に積もった灰で滑ったり汚れたりするのを防ぐため、長靴も非常に有効です。
その他:コンタクトレンズ利用者が注意すべきこと
コンタクトレンズ使用者は、火山灰が目に入った際にレンズと角膜の間で目を傷つけるリスクが高まります。災害時は衛生的なケアも難しくなるため、必ず予備の眼鏡も持ち出し袋に入れておきましょう。
在宅避難の鍵。「水・食料」の備蓄と賢いローリングストック法
ここでは、電気やガス、水道が止まった状態で自宅生活を送るための「備蓄」について解説します。持ち出すものだけでなく、「家に置いておくもの」の準備も防災の重要な柱です。
どのくらい必要?「水は1人3L/日、食料は最低3日分」が目安
飲料水と調理用の水を合わせて、「1人あたり1日3リットル」が推奨される量の目安です。これを「最低でも3日分」、可能であれば1週間分準備しておくと、ライフラインの復旧が遅れた場合でも安心です。食料も同様に、家族の人数×日数を計算して備えましょう。
備蓄を無理なく続ける「ローリングストック」の始め方
「1週間分の備蓄」と聞くと大変そうですが、「ローリングストック法」なら無理なく実践できます。
- STEP1: 少し多めに買う
普段から食べているパックご飯、レトルト食品、缶詰、カップ麺などを、いつもより少しだけ多めに購入します。 - STEP2: 古いものから食べる
戸棚の奥から古いものを取り出して、普段の食事で消費します。 - STEP3: 食べた分を買い足す
次の買い物の際に、食べた分だけ新しいものを買い足し、戸棚の奥にしまいます。
このサイクルを繰り返すだけで、常に一定量の非常食が家庭に備蓄されている状態を保つことができます。
おすすめ備蓄品リスト
- 主食: パックご飯、アルファ米、カップ麺、乾麺(パスタなど)、餅
- 主菜: レトルトカレー・丼、缶詰(サバ、ツナ、焼き鳥など)
- その他: インスタント味噌汁・スープ、野菜ジュース、フルーツ缶詰、お菓子
あなたの街のリスクは?自治体の「ハザードマップ」を確認しよう
モノの備えと同時に欠かせないのが、「情報の備え」です。ご自身の住む地域に、どのような災害リスクが潜んでいるのかを事前に知っておくことが、いざという時の避難行動に繋がります。
ハザードマップとは?どこで手に入る?
ハザードマップとは、地震による建物の倒壊危険度や、大雨による浸水、土砂災害などの危険箇所を地図上に示したものです。
お住まいの市町村の公式サイトで閲覧・ダウンロードできるほか、役所の窓口で紙の地図を配布している場合もあります。
(鹿児島市を例に)ハザードマップの見方と確認すべきポイント
例えば、鹿児島市の公式サイトのように、Web上で手軽に確認できる自治体も増えています。
ハザードマップを手に入れたら、以下の点を確認しましょう。
- 自宅や勤務先、学校は、危険区域(土砂災害警戒区域や浸水想定区域など)に入っているか。
- 指定されている避難所の場所はどこか。
- 避難所までの経路に、川や崖など危険な場所はないか。
避難場所と避難経路を家族で話し合っておこう
マップを確認したら、必ず家族全員で「災害時には、どこに、どの道を通って逃げるか」を話し合っておきましょう。この事前の共有が、家族の安否確認をスムーズにし、命を守ることに直結します。
まとめ:完璧な備えで、いつ来るかわからない災害に自信を持って立ち向かおう
今回は、南九州の地域特性に合わせた防災グッズと備蓄法を解説しました。
- 南九州では、一般的な地震対策に加え、「火山灰対策」が必須です。
- 完璧な備えとは、「基本の持ち出し袋」+「地域特化の追加グッズ」+「自宅備蓄」の3点セットで完成します。
- 無理なく続ける「ローリングストック法」は、備蓄のハードルを下げてくれる賢い知恵です。
完璧な備えは、災害そのものを防ぐことはできません。しかし、災害への恐怖を和らげ、いざという時に冷静に行動するための、何よりの「お守り」になります。
ぜひ、この記事のチェックリストを参考に、今日の買い物からでも、足りないものを一つ買い足すことから始めてみてください。その小さな一歩が、あなたとあなたの大切な家族を守る大きな力になるはずです。
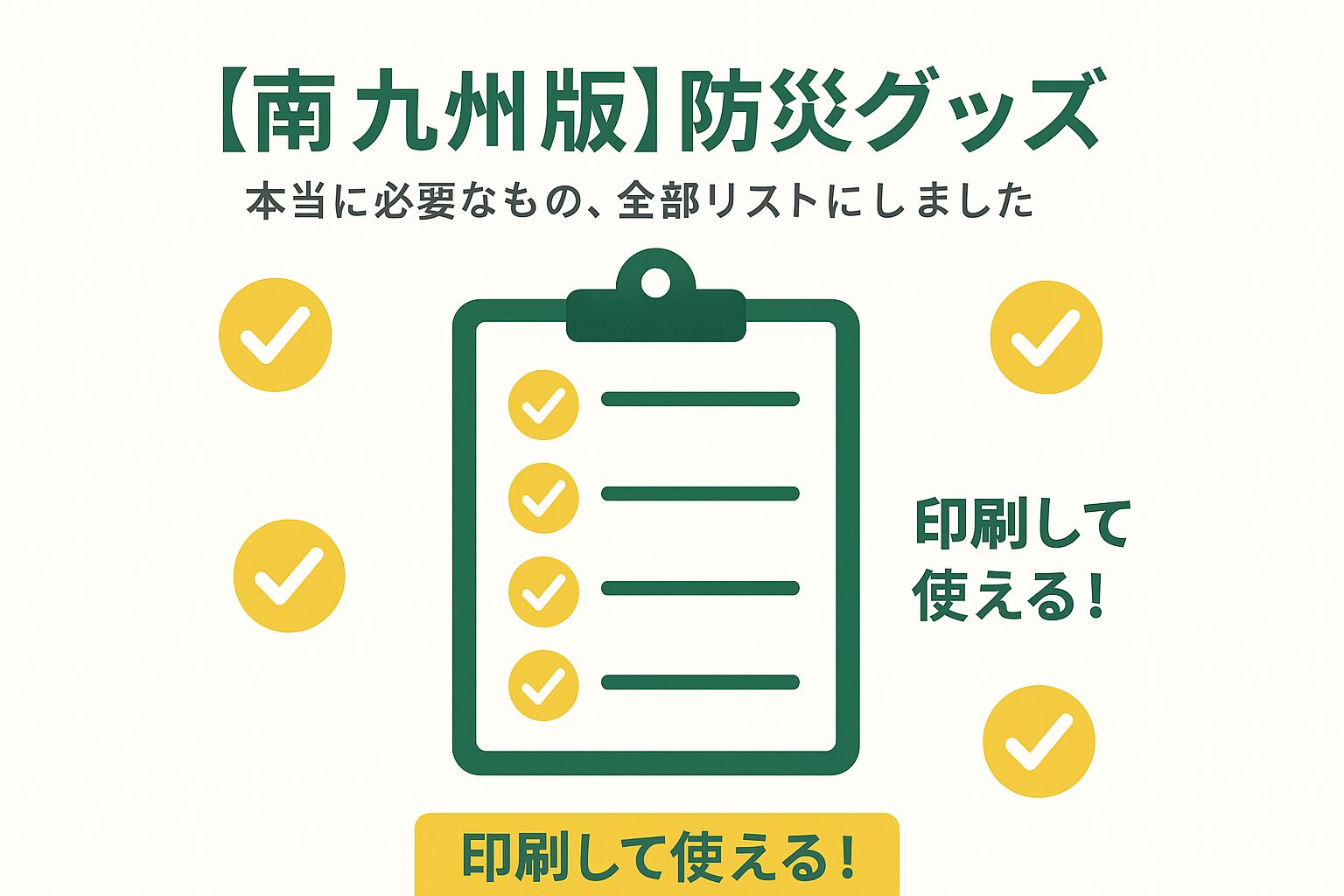
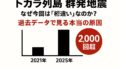

コメント