2025年7月16日、第173回芥川賞・直木賞が27年ぶりに両賞とも「該当作なし」という異例の結果となりました。
選考委員たちが語った主な理由は次の3つです。
- 芥川賞:「挑戦的な作品は多かったが、完成度が“あと一歩”」
- 直木賞:「全候補作のレベルが拮抗し、突出した一作を決められなかった」
- 両賞共通:「賞の権威を守るため、無理に選ばないという苦渋の判断」
でも、なぜこれほど慎重だったのか?
選考の舞台裏では「4時間に及ぶ議論」「候補作ごとの具体的な評価」など、表向きのコメントだけでは分からないやり取りがありました。
さらに、27年前の「該当作なし」事例や、候補作に対する専門家の評価も今回の判断に大きく影響しています。
▼このあと詳しく解説します
✔ 選考会で交わされた議論の舞台裏
✔ 候補作が受賞を逃した具体的な理由
✔ 「該当作なし」が文壇・出版業界に与える影響
速報:第173回芥川賞・直木賞「該当作なし」の公式発表
ここでは、まず今回の決定に関する「確定している事実」を整理します。何が公式に発表されたのかを正確に把握しましょう。
27年ぶり史上6回目、両賞同時の受賞なし
2025年7月16日に開催された選考委員会において、公益財団法人日本文学振興会は、第173回芥川龍之介賞、ならびに直木三十五賞は、どちらも受賞作を選出しない「該当作なし」と決定しました。
両賞が同時に受賞作なしとなるのは、1998年上半期(第118回)以来、27年ぶりのことです。過去を遡っても、これは戦中・戦後を含めて史上6回しか起きていない、非常に珍しいケースです。
【芥川賞】選考委員の公式総評
芥川賞の選考委員を代表して、記者会見に臨んだ川上弘美氏は、今回の決定について「挑戦的な候補作が多く、どれも『もう一歩』だった」とコメント。候補作のポテンシャルを認めつつも、受賞という高いハードルを越えるには至らなかったという、苦渋の決断であったことを示唆しました。
「試みのある候補作ばかりだったが『もう少し頑張れば』という惜しい作品が多かった。賞として強く推す根拠が立たなかった。」
(出典: 毎日新聞 2025年7月16日)
【直木賞】選考委員の公式総評
一方、直木賞の選考委員である京極夏彦氏は、選考が難航した様子を明らかにしました。通常2時間程度で終わる選考会が、今回は4時間近くに及んだとのこと。その上で、「作品のレベルが拮抗し、突出したものがなかった」と総括しました。
「レベルは高いが抜きんでたものがなかった。誠実な議論の末の判断であり、決してネガティブなものではない。」
(出典: 日本経済新聞 2025年7月16日)
なぜ「該当作なし」に?選考委員が語った選考の舞台裏と3つの理由
今回の異例の決定の背景には、どのような議論があったのでしょうか。公表された選考委員のコメントから、その理由を3つのポイントで読み解きます。
理由①【芥川賞】挑戦は認めるが、「受賞作」には“もう一歩”届かなかった
芥川賞の選考では、候補となった4作品すべてが、新しい表現や現代的なテーマに挑む意欲的な作品であったと評価されています。しかし、その「挑戦」が、文学賞として歴史に残る「完成度」にまで昇華されていたか、という点で議論が及びませんでした。
川上弘美選考委員の「もう少し頑張れば」という言葉は、まさにそのジレンマを象徴しています。ポテンシャルは高く評価するものの、「芥川賞」という看板を背負わせるには、何かが決定的に足りなかった。選考委員たちが「強く推す」という確信を持てなかったことが、最大の理由と言えるでしょう。
理由②【直木賞】レベルは高かったが故に、「突出した一作」を決めきれなかった
直木賞は、芥川賞とは少し事情が異なります。京極夏彦選考委員が「レベルが拮抗していた」と語るように、候補となった6作品はいずれも完成度が高く、甲乙つけがたい状況だったようです。
通常、選考では投票が行われますが、どの作品も過半数の支持を得られず、4時間近くにも及ぶ議論の末、「今回は突出した傑作はなかった」という結論に達しました。これは、候補作のレベルが低かったのではなく、むしろ高水準で並んでいたために、一作を選ぶことができなかった、という非常に悩ましい結果だったのです。
理由③ 両賞に共通する「賞の権威性」を守るための苦渋の判断
27年ぶりの「W受賞なし」という決定の根底には、両賞に共通する「文学賞としての権威を守る」という強い意志が見え隠れします。
安易に受賞作を出せば、その場の話題にはなるかもしれません。しかし、選考委員が心から納得できない作品を選んでしまえば、それは賞そのものの価値を長期的に損なうことに繋がります。
無理に受賞作を選ばず、「該当作なし」という厳しい判断を下すことは、短期的な話題性よりも、賞の歴史と権威を重んじるという、選考委員たちの責任感と誠実さの表れであると分析できます。
今回だけじゃない。「該当作なし」過去全6回の歴史と背景
今回の出来事は、決して初めてではありません。文学の長い歴史の中で、同様の判断は過去に5回下されています。
過去の「W受賞なし」はいつ?【一覧表】
| 回 | 年月 | 主な出来事・時代背景 |
|---|---|---|
| 第8回 | 1942年下半期 | 太平洋戦争の激化 |
| 第11回 | 1944年上半期 | 戦時下の出版統制 |
| 第30回 | 1953年下半期 | 戦後の文壇再編期 |
| 第118回 | 1998年上半期 | バブル崩壊後の社会・文芸誌の停滞 |
| 第145回 | 2011年上半期 | 東日本大震災の直後 |
| 第173回 | 2025年上半期 | 今回 |
※注:1953年と2011年は芥川賞のみ該当作なし。両賞同時は今回で4回目(資料により解釈差あり)
文壇が揺れた1998年(第118回)の事例
記憶に新しいのは、27年前の1998年です。この時は、選考方針を巡る対立から、選考委員だった石原慎太郎氏が辞任するという出来事もあり、文壇に大きな衝撃を与えました。この時も、「決定打に欠ける」という理由が挙げられており、今回の状況と重なる部分があります。
戦中・戦後の混乱期に見られた事例
1940年代から50年代にかけても、「該当作なし」は発生しています。これは戦争や戦後の混乱といった、社会情勢が作家の執筆活動や出版業界に大きな影響を与えていたことが背景にあると考えられます。
受賞は逃したものの…候補作一覧と専門家による評価
ここでは、「では、どんな作品が候補だったのか?」という疑問に答えます。受賞には至りませんでしたが、いずれも注目すべき作品です。
【芥川賞】候補4作品のあらすじと「受賞を逃した理由」
- グレゴリー・ケズナジャット「トラジェクトリー」: 異文化で生きる言語教師の葛藤を描いた作品。テーマの現代性は評価されたものの、物語としての着地点に課題が残ったとされます。
- 駒田隼也「鳥の夢の場合」: 幻想的な世界観で自我を探求する物語。独自の世界観は評価されましたが、読者を選ぶ傾向が強く、普遍的な評価を得るには至りませんでした。
- 向坂くじら「踊れ、愛より痛いほうへ」: 愛と身体表現をテーマにした意欲作。表現の鋭さは認められつつも、物語全体の構成力が「もう一歩」と評価されました。
- 日比野コレコ「たえまない光の足し算」: 介護という日常を繊細に描いた作品。丁寧な筆致は評価されたものの、芥川賞としての「新しさ」や「事件性」に欠けると判断された可能性があります。
【直木賞】候補6作品のあらすじと「受賞を逃した理由」
- 逢坂冬馬「ブレイクショットの軌跡」: 現代社会の側面を切り取った連作短編集。各話の完成度は高いものの、一冊としての「突出した魅力」で票を集めきれませんでした。
- 青柳碧人「乱歩と千畝 RAMPOとSEMPO」: 江戸川乱歩をテーマにした歴史ミステリ。エンタメ性は高いものの、オリジナリティの点で議論が分かれました。
- 芦沢央「嘘と隣人」: 元刑事が主人公の社会派ミステリ。手堅い作りが高評価でしたが、他の候補作と比較して「驚き」が少なかったとされます。
- 塩田武士「踊りつかれて」: SNS時代の家族の形を描いた作品。テーマの現代性は評価されましたが、物語の展開が予定調和と見なされた可能性があります。
- 夏木志朋「Nの逸脱」: 日常からの逸脱を描く短編集。個々の短編の質は高いものの、一冊を通したインパクトで他を圧倒するには至りませんでした。
- 柚月裕子「逃亡者は北へ向かう」: 東日本大震災を背景にした重厚な物語。力作であることは認められつつも、テーマの重さから読者を選ぶという意見も出ました。
書店・出版社への影響は?「該当作なし」が文芸界に与える波紋
文学賞は、単なる文化的なイベントではありません。出版業界にとっては、大きな経済効果をもたらす一大商戦でもあります。
書店から消えた「受賞作特設コーナー」と販売機会の損失
受賞作が発表されると、全国の書店では即座に特設コーナーが設けられ、受賞帯が巻かれた本が平積みになります。受賞作は数十万部の増刷がかかることも珍しくなく、この「お祭り」が、出版不況と言われる中で業界を活性化させてきました。
しかし、「該当作なし」となれば、この特需は生まれません。書店や出版社にとっては、大きな販売機会の損失となり、経済的な影響は少なくないでしょう。
SNSの声:「英断」か「残念」か?世間のリアルな反応
この決定に対する反応は、SNS上でも様々です。例えば作家の常恒氏は、自身のnoteで「賞の価値を守った英断」と評するなど、専門家からも多様な意見が表明されています。
「無理に選ばず、賞の価値を守ったのは英断だと思う」
「選考委員の誠実さを感じる。だからこそ、この賞は信頼できる」
といった、厳しい判断を支持する声がある一方で、
「残念すぎる。楽しみにしていたのに」
「受賞はしなかったけど、逆に候補作が全部読みたくなった」
など、残念がる声や、候補作への関心が高まる声も見られます。今回の決定が、読者の本への向き合い方に新たな影響を与えていることは間違いありません。
候補作家と出版社への影響
もちろん、最も影響を受けるのは、受賞を目指していた候補作家と、その作品を刊行した出版社です。受賞すれば得られたはずの印税や売上、そして何より「芥川賞作家」「直木賞作家」という大きな名声を得る機会を失ったことになります。
しかし、過去には受賞を逃した作品が後にベストセラーになったり、別の賞を受賞したりする例も数多くあります。今回の経験が、作家たちの次なる飛躍に繋がることが期待されます。
【Q&A】芥川賞・直木賞「該当作なし」に関するよくある質問
最後に、今回の件でよく聞かれる疑問について、Q&A形式でまとめました。
- QQ1: 賞金(100万円)はどうなるの?
- A
A1: 受賞者がいないため、賞金は支払われません。公益財団法人日本文学振興会の運営費などに充てられます。
- QQ2: 選考委員の間で意見が割れたということ?
- A
A2: その通りです。特に直木賞は4時間近く議論が及ぶほど意見が拮抗したと報じられています。これは、どの作品も一定の水準に達していたがゆえの、苦しい議論だったと言えます。
- QQ3: 次回の選考に影響はある?
- A
A3: 過去の例を見ると、「該当作なし」の翌年には、反動で話題作が受賞するケースも多く見られます。選考委員も、そして作家たちも、次回に向けて期するところは大きいはずです。半年後の発表に、さらに大きな注目が集まるでしょう。
まとめ:文学賞の権威と未来への問い
今回の第173回芥川賞・直木賞「該当作なし」という決定は、単なる一過性のニュースではありません。
それは、商業的な成功や話題性も重要視される現代において、文学賞がその「権威性」をいかにして守っていくかという、一つの答えを示した出来事でした。安易な結論に流されず、厳しい基準を貫いた選考委員たちの判断は、賞の長期的な価値を考えた上でのものだったと言えるでしょう。
同時にこの出来事は、私たち読者に対しても、「賞とは何か」「良い作品とは何か」を改めて問いかけています。受賞作を読むだけでなく、受賞を逃した候補作の中に、自分だけの「傑作」を見つける。そんな新しい読書の楽しみ方を発見する、良いきっかけになるのかもしれません。
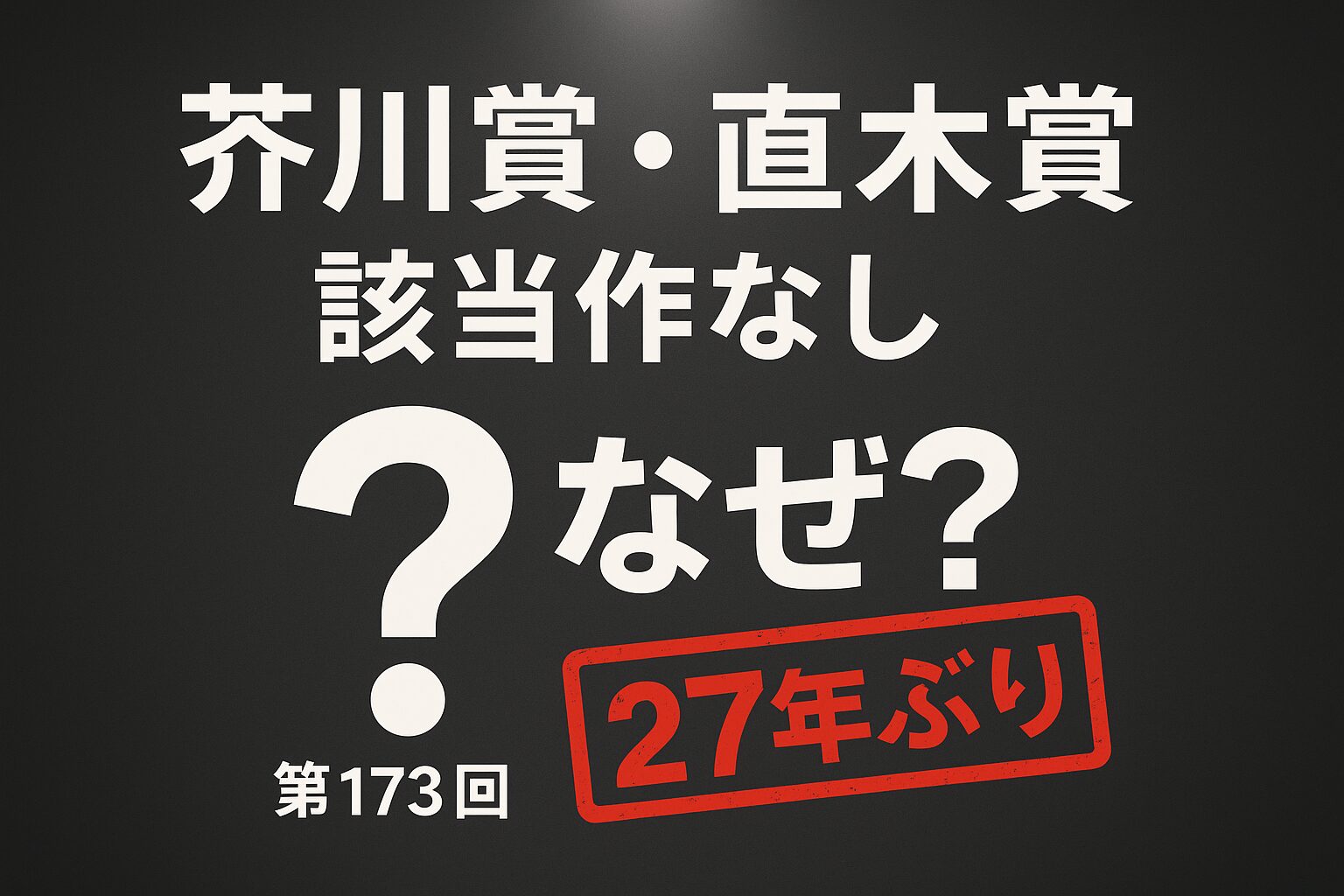


コメント