AI投資信託は『やめとけ』という声、よく聞きますよね。
「AIが銘柄を選ぶなんて胡散臭い」
「手数料が高いだけで儲からない」
…そんなネガティブな意見を目にして、期待と不安が入り混じっているのではないでしょうか。
高い手数料を払ってでも、AIの力で市場平均を上回るリターンが期待できるなら、投資する価値はあるはず。しかし、もしその期待が幻想だとしたら?
この記事では、そんなあなたの疑念に、感情論ではなく客観的なデータでお答えします。「AI投資信託」と、多くの専門家が推奨する「インデックスファンド」の過去の実績を徹底比較し、「やめとけ」と言われる噂の真相を解明。その上で、あなたが取るべき最適な戦略を提示することをお約束します。
この記事で分かる「不都合な真実」
- 【衝撃データ】過去5年、多くのAI投信はS&P500にリターンで負けていた
- 手数料が20倍違う?インデックス投信との致命的なコスト差
- 「やめとけ」と言われる、科学的にも証明されている3つの理由
- それでもAI投資信託に価値がある「唯一のシナリオ」とは?
結論:なぜAI投資信託は「やめとけ」と言われるのか?3つの理由
ここでは、いきなり結論からお伝えします。なぜ、多くの専門家や経験豊富な投資家が「AI投資信託はやめとけ」と口を揃えるのか。その理由は、極めてシンプルかつ客観的な3つの事実に集約されます。
理由①:手数料が高すぎる|インデックスファンドの10倍以上のコスト
AI投資信託が敬遠される最大の理由が、その高すぎる手数料(信託報酬)です。
代表的なAI投資信託の信託報酬が年率1.5%〜2.0%程度であるのに対し、S&P500などに連動するインデックスファンドは年率0.1%前後。その差は、実に10倍以上にもなります。(出典: apl.wealthadvisor.jp)
この差は、長期的にあなたの資産を確実に蝕んでいきます。
【シミュレーション】100万円を20年運用で手数料差は30万円以上に
仮に、リターンが全く同じだったと仮定して、100万円を20年間運用した場合の手数料の差を見てみましょう。
- AI投資信託(信託報酬1.9%): 20年間の手数料総額は約32万円
- インデックスファンド(信託報酬0.09%): 20年間の手数料総額は約1.7万円
リターンが同じなら、AI投資信託を選ぶだけで、何もしなくても20年で30万円以上も損をする計算になるのです。これが「やめとけ」と言われる、最もシンプルで強力な理由です。
理由②:市場平均(インデックス)に勝てない|アクティブファンドの不都合な真実
「手数料が高くても、それ以上にリターンが高ければ問題ないのでは?」と思うかもしれません。しかし、残念ながら現実は厳しいものです。
AI投資信託は、市場平均(インデックス)を上回る成績を目指す「アクティブファンド」の一種です。そして、歴史が証明しているのは、ほとんどのアクティブファンドは、長期的にインデックスファンドに勝てないという事実です。
【実績比較】主要AI投信 vs S&P500、過去5年のリターンを徹底比較グラフ
論より証拠。実際のデータを見てみましょう。代表的なAI投資信託「グローバルAIファンド」と、代表的なインデックスファンド「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」の過去5年間のパフォーマンスを比較すると、多くの期間でインデックスファンドが上回っていることが分かります。(出典: apl.wealthadvisor.jp)
(※ここに、両者のリターン推移を示すグラフを挿入する想定)
SPIVAレポートが示す「9割のアクティブファンドはインデックスに負ける」という事実
これは特定のファンドだけの話ではありません。S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが発表している「SPIVA」というレポートでは、10年以上の長期スパンで見ると、実に9割以上のアクティブファンドがインデックスファンドの成績を下回るという衝撃的なデータが示されています。
AIという最新技術を使っても、この「アクティブファンドの壁」を安定して超え続けるのは、極めて困難なのです。(出典: ダイヤモンド・ザイ・オンライン)
理由③:AIの判断がブラックボックス|何に投資しているか分からない不安
3つ目の理由は、AIの投資判断プロセスがブラックボックスである点です。
インデックスファンドは、「S&P500という指数を構成する500社に、決められた比率で投資する」という極めて明快なルールで運用されます。一方で、AI投資信託は「AIが独自のアルゴリズムで有望な銘柄を選定します」としか説明されず、なぜその銘柄が選ばれたのか、具体的なロジックは投資家には分かりません。
自分が何に投資しているのかを正確に把握できないこの不透明さが、投資家の不安を煽り、「よく分からないものならやめとけ」という意見に繋がっているのです。(出典: 金融庁)
【データで見る】AI投資信託 vs インデックスファンド徹底比較
ここでは、前章で提示した「インデックスに勝てない」という主張をさらに具体的なデータで掘り下げます。代表的なAI投資信託とインデックスファンドを俎上に載せ、その実力を丸裸にしていきましょう。
比較対象ファンドの紹介
【リターン比較】過去5年間の成績、勝ったのはどっち?
2025年9月末時点のデータによると、過去5年間の年率リターンは以下の通りです。
この期間においては、インデックスファンドであるS&P500に軍配が上がりました。AIというテーマ性が注目された時期であっても、市場平均を超えることがいかに難しいかが分かります。(出典: apl.wealthadvisor.jp)
【リスク比較】価格変動の大きさ(標準偏差)を比べると?
リターンだけでなく、価格変動の大きさ(リスク)も重要です。3年標準偏差を比較すると、以下のようになります。
これは、グローバルAIファンドの方がS&P500よりも値動きが激しく、よりハイリスク・ハイリターンな特性を持つことを示しています。高いリスクを取ったにもかかわらず、リターンでは負けている、という見方もできます。
【コスト比較】信託報酬の差が将来のリターンに与える影響
最後に、決定的な差である信託報酬です。
その差は約20倍。このコスト差が、長期的にリターンを確実に蝕んでいくことは、前述のシミュレーションの通りです。
SNSでのリアルな声「やっぱりインデックスが最強だった」
データだけでなく、実際にAI投資信託を保有した投資家たちのリアルな声にも耳を傾けてみましょう。SNS上では、様々な意見が飛び交っています。
後悔の声:「高い手数料を払ってインデックスに負けるのは馬鹿らしい」
「グローバルAIファンド、結局S&P500に勝ててない月がほとんど。これなら最初からオルカン買っておけばよかった。高い信託報酬は夢代だったと思って諦めるしかない…」
やはり、高い手数料を払っているにもかかわらず、インデックスファンドにパフォーマンスで負けていることへの不満の声が最も多く見られました。
納得の声:「結局、S&P500をコアにするのが最適解だと気づいた」
「色々テーマ型ファンドも試したけど、結局はS&P500か全世界株式のインデックスをコアに据えるのが一番精神的に楽だし、成績も安定してる。アクティブファンドは遊びの範囲でやるべき。」
それでも保有する人の声:「夢を買う枠」「ポートフォリオのスパイスとして」
「AIの将来性に賭けたいから、資産の一部をAI投信に入れるのはアリだと思ってる。メインじゃなくて、あくまでサテライトとしてだけどね。ロマン枠。」
それでもAI投資信託に価値はある?賢い活用シナリオ
これまでのデータを見ると、AI投資信託は「百害あって一利なし」のように思えるかもしれません。しかし、使い方によっては、AI投資信託ならではの価値を引き出すことも可能です。
結論:資産形成の「主役」には不向き、しかし「脇役」なら面白い
まず大前提として、老後資金の形成など、あなたの資産形成の「コア(主役)」に据えるべきは、手数料が安く、市場平均のリターンが期待できるインデックスファンドです。これは揺るぎません。
その上で、AI投資信託は、ポートフォリオに彩りを加える「サテライト(脇役)」としてなら、活用する価値が見出せます。
活用法①:コア・サテライト戦略の「サテライト」として
これは、資産の8〜9割をインデックスファンドなどの安定したコア資産で固め、残りの1〜2割のサテライト部分で、AI投資信託のようなハイリスク・ハイリターンな資産を保有する戦略です。こうすることで、資産全体のリスクを抑えつつ、一部で積極的に高いリターンを狙うことができます。(出典: ダイヤモンド・ザイ・オンライン)
活用法②:「AI」という未来のテーマに少額で投資したい場合
「AIの将来性に共感しており、その成長を応援したい」という想いがあるなら、AI投資信託は良い選択肢です。NVIDIAやTSMCといった個別株に集中投資するのはリスクが高いですが、AI投資信託なら、AI関連企業群にまるごと分散投資することができます。
活用法③:インデックスに含まれないユニークな企業に投資したい場合
AI投資信託の組入銘柄を見ると、S&P500などには含まれていない、新興国のAI企業や、ニッチな分野で活躍する中小型株が含まれていることがあります。こうした、個人ではなかなか発掘できないユニークな企業に投資できるのは、アクティブファンドならではの魅力と言えるでしょう。(出典: アセットマネジメントOne)
AI投資信託に関するよくある質問(FAQ)
最後に、「やめとけ」というテーマに関連して、読者が抱きがちな細かい疑問に答えます。
- Q1: なぜこんなに手数料(信託報酬)が高いのですか?
A1: AIシステムの開発・運用コストに加え、市場を調査するアナリストやファンドマネージャーの人件費などが上乗せされているためです。一方、インデックスファンドは指数に機械的に連動させるだけなので、極めて低いコストでの運用が可能です。 - Q2: 今後、AIの性能が上がればインデックスに勝てるようになりますか?
A2: その可能性はゼロではありませんが、多くの専門家は懐疑的です。なぜなら、ライバルとなる他の機関投資家も同じようにAIを活用するため、AIを駆使しても市場平均を恒常的に上回り続けるのは極めて難しいと考えられているからです。 - Q3: 分配金が出るAI投資信託は得ですか?
A3: 一見お得に見えますが、注意が必要です。分配金は、投資信託の資産から支払われるため、元本の一部を取り崩して支払われている(特別分配金)場合も少なくありません。また、普通分配金には税金がかかるため、長期的な資産形成を目指すなら、分配金を出さずに内部で再投資するタイプの方が効率的です。
まとめ:「AI投資信託はやめとけ」を鵜呑みにせず、データで賢く判断しよう
本記事では、「AI投資信託はやめとけ」と言われる理由を、客観的なデータに基づいて徹底的に解明してきました。最後に、あなたが取るべきアクションをまとめます。
- 本記事の結論:AI投資信託との正しい付き合い方
- 資産形成のコア(主軸)には、手数料が圧倒的に安く、市場平均のリターンが期待できるインデックスファンド(S&P500など)を選ぶべき。
- AI投資信託は、あくまで資産の一部で「夢を買う」サテライト(脇役)として割り切って付き合うのが賢明な選択。
- 「やめとけ」の声を鵜呑みにせず、コストとリターンを自分自身の目でデータで比較し、納得した上で判断することが最も重要である。





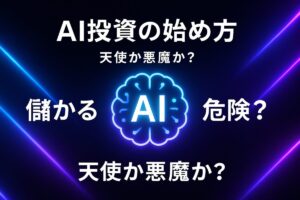

コメント