
「金融危機が起きれば、安全資産である金の価格は上がるはず」
多くの人がそう信じています。しかし、2008年のリーマンショックでは、その常識が一時的に覆されました。危機直後、金価格はなぜか急落したのです。

この記事では、リーマンショックという歴史的な金融危機において、金相場が「下落」と「高騰」という2つの全く異なる顔を見せた理由を、当時のデータと経済の仕組みから徹底的に解き明かします。
「デレバレッジ」による換金売りとは何か? なぜその後の「量的緩和(QE)」が金価格を歴史的な高値へと押し上げたのか?
この複雑なメカニズムを理解することは、次の金融危機に備え、あなたの資産を賢く守るための羅針盤となるでしょう。
この記事でわかること
- 「有事の金」も下落する?危機初期の意外な値動きの真相
- 下落と高騰を分けた2つのキーワード「デレバレッジ」と「量的緩和」
- 【データで比較】金・株・原油、リーマンショックで最も下落したのは?
- 次の金融危機で本当に役立つ、歴史からの教訓
※この記事では「リーマンショック」の事例に特化して解説します。より広範な「米国債デフォルト」という究極のシナリオと金の価値の全体像を把握したい方は、まずはこちらの総合記事をご覧ください。
→ もし米国債がデフォルトしたら金価格は?歴史に学ぶ究極のリスクヘッジ
なぜ?リーマンショック直後に金価格が「下落」した本当の理由
ここでは、多くの人が「安全資産」と信じる金が、なぜ金融危機発生直後に売られたのか、その直感に反する値動きの背景にある金融市場特有のメカニズムを、より深く掘り下げて解説します。
金相場におけるリーマンショックの影響は、単純な一言では語れません。
あらゆる資産が売られた「デレバレッジ」の嵐
2008年9月15日のリーマン・ブラザーズ経営破綻は、世界中の金融市場に激震を走らせました。サブプライムローン問題に端を発した信用不安は一気に拡大し、金融機関は巨額の損失を抱えることになります。
このとき、市場で起きていたのが「デレバレッジ」です。金融機関やヘッジファンド、個人投資家は、損失の拡大を防ぎ、借入金を返済するために、保有している資産を投げ売りし始めました。
重要なのは、この投げ売りは資産の種類を問わなかったという点です。株式や不動産はもちろん、比較的堅調に推移していた金でさえも、売却の対象となりました。(出典: 日本経済新聞)
投資家が金さえも手放した「現金化」の動き
なぜ、安全資産であるはずの金まで売られたのでしょうか。その答えは「現金(キャッシュ)の確保」にあります。
金融危機が深刻化すると、市場では流動性が枯渇し、誰もがお金を貸したがらなくなります。このような状況下では、企業も投資家も、日々の支払いや損失の穴埋めのために、何よりもまず現金を確保しようと動きます。
そのため、たとえ利益が出ていたとしても、すぐに現金化できる資産はすべて売却の対象となります。金は流動性が高く、世界中の市場でいつでも売買できるため、この「現金化」の動きの中で、一時的に売られる運命にあったのです。
2008年9月から10月にかけて、金価格が約900ドルから700ドル台へと約30%も急落したのは、このためです。(出典: ソニーフィナンシャルグループ レポート)
【用語解説】デレバレッジ
企業や個人が、借入(レバレッジ)の比率を引き下げることです。金融危機時には、資産価格の下落によって担保価値が減少し、追加の証拠金(追証)の支払いが必要になることがあります。
その支払いのために保有資産を売却せざるを得なくなり、さらなる資産価格の下落を招く悪循環に陥ることがあります。(出典: 日本銀行 金融市場レポート)

データを整理していて意外だったのは、多くの人が「金融危機=金は買い」という一直線のイメージを持ちがちですが、リーマンショックの初期には「換金売り」による金価格の下落が起きていた点です。
SNS上でも「なぜあの時、金は下がったの?」という疑問は今でも見られます。これは、次の危機でも多くの人が見落とす可能性のある、重要なポイントと言えるでしょう。
一転して金価格が「高騰」に転じた金融緩和のインパクト
危機発生から数ヶ月後、下落していた金価格は一転して力強い上昇トレンドに入ります。その背景には、各国中央銀行、特に米連邦準備制度理事会(FRB)による前例のない金融政策がありました。
ここでは、金相場を復活させた量的緩和(QE)のメカニズムを詳しく見ていきましょう。
FRBによる大規模「量的緩和(QE)」の開始
市場の混乱を収拾し、景気を底支えするため、FRBは2008年末から「量的緩和(QE1)」と呼ばれる非伝統的な金融政策に踏み切りました。
これは、中央銀行が国債や住宅ローン担保証券(MBS)などを大量に買い入れて、市場に大量の資金(ドル)を供給する政策です。
QE1(2008年末~2010年春)では総額約1.7兆ドル、その後のQE2、QE3と続く一連の量的緩和によって、市場には前例のない規模のドルが供給されることになりました。(出典: 東海東京証券 レポート)
ドルへの不信とインフレ懸念が金買いを呼んだ
市場に大量のドルが供給されたことは、2つの大きな影響をもたらしました。
- ドルの価値の希薄化: 市場に出回るドルの量が増えれば、その希少価値は薄まります。投資家は、将来的にドルの価値が下落する(インフレが起きる)ことを懸念し始めました。
- 代替資産への逃避: ドルへの信認が揺らぐ中で、投資家は価値の保存手段として、特定の国家の信用に依存せず、発行量に物理的な上限がある「金」に資金をシフトさせました。
この結果、金ETFへの資金流入が加速し、金価格は2011年夏には1,900ドルを超える歴史的な高値を記録するに至ったのです。(出典: JETROレポート)
【用語解説】量的緩和(QE)
中央銀行が、公開市場操作で国債などの金融資産を買い入れることにより、金融市場に大量の資金を供給する金融緩和政策のことです。金利の引き下げや資産価格の上昇を通じて、経済活動を刺激する効果が期待されます。(出典: ダイヤモンド・オンライン)

ここまで見てきたように、「デレバレッジによる下落」と「量的緩和による高騰」は、金融危機の異なるフェーズで起きる現象であり、セットで理解することが重要です。
単に「有事の金は買い」と短絡的に考えるのではなく、危機時の経済状況と中央銀行の政策対応を総合的に判断する視点が不可欠と言えるでしょう。
【データで比較】リーマンショック時の各資産の値動き
リーマンショック時、他の資産クラスは金と比較してどのように動いたのでしょうか。実際のデータを見ることで、金が「安全資産」と呼ばれる所以がより明確になります。
ここでは、金と株式、原油、そして米国債の値動きを比較分析します。
金 vs 株式(S&P500):どちらが早く回復したか?
リーマンショックで最も大きな打撃を受けた資産の一つが株式です。
米国の代表的な株価指数であるS&P500は、2008年9月から2009年3月にかけて約50%も下落しました。一方、同期間の金の下落は約30%に留まりました。(出典: ソニーフィナンシャルグループ レポート)
さらに重要なのは、その後の回復力です。金は量的緩和を背景にいち早く上昇に転じ、2011年には史上最高値を更新しました。
しかし、S&P500がリーマンショック前の水準を回復するには、さらに長い年月を要したのです。(出典: マネックス証券)
金 vs 原油:コモディティの中でも明暗が分かれた理由
同じコモディティ(商品)でありながら、金と原油の値動きは対照的でした。
世界経済の急減速懸念から、景気の動向に敏感な原油の価格は、2008年7月の高値145ドルから年末には40ドル台へと約70%も暴落しました。
これに対し、金は工業需要よりも「通貨」や「価値の保存」としての側面が強く評価されたため、資金の逃避先として選ばれ、価格が上昇しました。この違いが、同じコモディティの中でも明暗を分けた理由です。
安全資産の代表格「米国債」との比較
危機発生時、投資家はリスクの高い株式などから、より安全とされる米国債へと資金を移動させました。これは「質への逃避」と呼ばれます。
この動きにより米国債の価格は上昇し、利回りは急低下しました。(出典: 日本銀行 金融市場レポート)
金も短期的には売られましたが、その後の量的緩和局面では、ドルへの不信感から米国債と同様に安全資産として買われる展開となりました。危機に対して異なる反応を見せつつも、長期的にはどちらも資産を守る役割を果たしたと言えます。

各資産の騰落率の数字を比較すると、金は他のリスク資産に対して「下落率の低さ」と「回復の速さ」という2つの点で優位性を持っていたことが明確に見て取れます。
しかし、一時的には金も下落したという事実は、常に頭に入れておくべき重要な教訓です。
リーマンショックの教訓|次の金融危機で資産を守るために
過去の危機から学ぶべき最も重要なことは何でしょうか。
リーマンショックの経験は、将来の不確実性に備えるための3つの重要な教訓を私たちに与えてくれます。この知識は、次の金融危機であなたの資産を守るための指針となるはずです。
教訓1:「有事の金」も短期的には下落するリスクを認識する
「有事の金」という言葉は、長期的には真実ですが、常に正しいわけではありません。
リーマンショックが示したように、金融システム全体の流動性が失われるような極端な信用収縮の局面では、金でさえも短期的な換金売りの対象となる可能性があります。
このリスクを理解しておくことは、パニック売りを避け、冷静な投資判断を維持するために不可欠です。
教訓2:危機の本質と中央銀行の政策がその後の相場を決定づける
金価格の動向を予測する上で、危機が「信用収縮」の段階なのか、それとも中央銀行による「金融緩和」の段階なのかを見極めることが極めて重要です。
リーマンショックでは、FRBによる迅速かつ大規模な量的緩和が、その後の金価格の歴史的な高騰に決定的な影響を与えました。
次の危機においても、中央銀行の政策対応が相場の方向性を決定づける最大の要因となるでしょう。
教訓3:時間分散と資産分散の重要性を再確認する
リーマンショックの経験は、特定のタイミングに一点集中で投資することの危険性と、資産を複数のクラスに分散させることの重要性を改めて示しました。
特に、危機時に異なる値動きをする傾向がある金と株式をポートフォリオに組み入れることは、全体のリスクを低減させる上で非常に有効です。
また、一度にまとめて投資するのではなく、定期的に一定額を投資する「ドルコスト平均法」のような時間分散の手法も、高値掴みのリスクを避けるために役立ちます。
▼次のステップ:通貨システムの歴史を学ぶ
リーマンショックのような危機を経て、現在の通貨システムそのものに疑問を持つ方もいるでしょう。その根源を「金本位制」の歴史から紐解くこの記事が、次のステップです。
→ 金本位制の復活はあり得る?金価格の未来と通貨制度の課題を考察

まとめ:リーマンショックから学ぶ金投資の普遍的な原則
最後に、この記事で解説してきた内容を総括し、リーマンショックの経験から得られる金投資の普遍的な原則をまとめます。
【総復習】金相場の2つの局面と重要ポイント
- 危機初期の下落局面:
- 要因: 金融機関や投資家による「デレバレッジ」が引き起こした、利益確定や損失補填のための現金化売りが主要因。
- 教訓: 「有事の金」という言葉を過信せず、極端な金融危機下では金も短期的には下落するリスクがあることを認識する。
- 危機後の高騰局面:
- 要因: FRBによる大規模な「量的緩和(QE)」が市場に大量のドルを供給し、将来のインフレ懸念とドルへの信認低下を引き起こしたことが主要因。
- 教訓: 金価格の長期的な方向性は、中央銀行の金融政策に大きく左右される。
- 他資産との比較:
- 優位性: 株式や原油といった他のリスク資産と比較して、下落率は限定的であり、その後の回復も早かった。
- 最大の教訓:
- 短期的な価格変動に一喜一憂せず、金が持つ「価値の保存」という本質的な役割を理解し、長期的な視点で資産ポートフォリオの一部として保有することが重要。
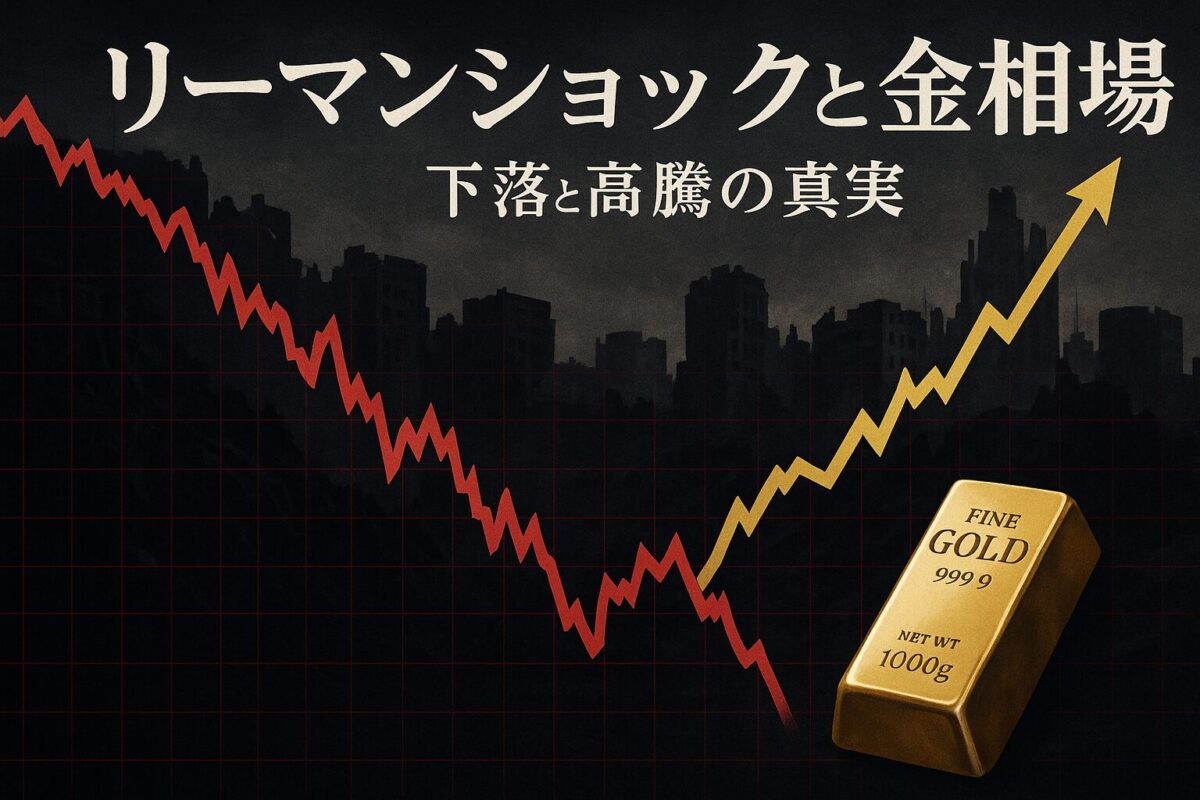



コメント