金は「安全資産」と呼ばれ、経済の不確実性が高まると買われる傾向にあります。
しかし、歴史を振り返ると、金相場も例外なく大暴落を経験してきました。過去の暴落のニュースを見ると漠然とした不安を感じ、次の暴落が来たらどうすれば良いか途方に暮れている方もいるかもしれません。
この記事では、金相場を襲ったリーマンショック、テーパータントラム、コロナショックという3つの主要な暴落事例を詳細に分析します。それぞれの暴落がなぜ起こり、金価格がどのように変動し、そしてどのように回復したのか。

また、暴落の最終局面で現れる「セリングクライマックス」や、「出来高」から底打ちサインを読み解く方法、さらには感情的な「狼狽売り」を防ぐための具体的なリスク管理術まで、過去の教訓から未来のリスクに備える知識を体系的に解説します。
この記事を読めば、過去の暴落事例から教訓を得て、将来の急落リスクに冷静に備えることができるようになるでしょう。暴落時の「底打ちサイン」を理解し、リスク管理に自信を持って金相場と向き合えるようになることを目指します。
この記事でわかること
- リーマンショックなど過去の金相場暴落時のリアルな値動き
- なぜ「安全資産」の金も暴落時に一時的に売られるのか
- 暴落の最終局面「セリングクライマックス」の見極め方
- 「出来高」から暴落の底打ちサインを読み解く方法
- 次の暴落に備えるための具体的なリスク管理術
※この記事では「過去の暴落事例分析」に特化して解説します。Yahoo!ファイナンスを使って現在のチャートを分析する基本手順については、こちらの総合記事をご覧ください。
→ Yahoo!金価格チャート分析の完全ガイド|見方から設定まで徹底解説

【事例分析】過去の金相場はどのように暴落し、回復したのか?
ここでは、金相場の歴史に残る3つの主要な暴落事例を振り返り、それぞれの原因と、その後の金価格の動きをチャート分析の観点から掘り下げます。過去の教訓は、未来のリスクを乗り越えるための最高の羅針盤となります。
リーマンショック(2008年):「換金売り」で金も一時下落
2008年9月15日のリーマン・ブラザーズ破綻を契機とした世界的金融危機「リーマンショック」は、金相場にも大きな影響を与えました。
信用収縮と流動性逼迫が同時進行する中で、金も他のリスク資産同様に大幅下落を経験したのです。(出典: politicalstaples)
なぜ安全資産の金まで売られたのか?「換金売り」のメカニズム
金は「安全資産」とされながらも、リーマンショック直後には現金確保のための「換金売り」が優勢となり、一時的に下落しました。
多くの投資家が、あらゆる資産を売却して手元に現金を確保しようとしたため、金も例外ではなかったのです。2008年10月には、海外金相場が1トロイオンス716–720ドル台まで急落する局面も見られました。(出典: nanboya)
その後のV字回復と量的緩和が与えた影響
しかし、金相場はその後急速に回復します。FRB(米連邦準備制度理事会)による大規模利下げと量的緩和でドル安・インフレ懸念が強まり、安全資産としての金需要が高まったためです。
金価格はショック前水準を上回る長期上昇トレンドに転じ、安全資産としての役割を再認識させました。(出典: gold.mmc+2)

リーマンショックは「有事の金」神話が一時的に崩れた瞬間であり、どんな資産も流動性危機の前では無力であるという教訓を示しています。しかし、その後の回復力と金融緩和の恩恵を受けた金相場の動きは、リスク資産とは異なる金の特性を示唆すると言えるでしょう。
テーパータントラム(2013年):「米金利上昇」が引き起こした急落
2013年にFRBが量的緩和縮小(テーパリング)を示唆したことで、市場が過剰に反応し、米長期金利が急騰、新興国資産が急落しました。これがテーパータントラムです。(出典: smd-am)
FRBの金融緩和縮小観測が金相場を直撃した理由
テーパータントラム時の金価格急落の主因は、米長期実質金利の上昇でした。金は利息を生まない無利子資産であるため、金利が上昇すると、利回りを持つ他の資産(特に債券)の魅力が相対的に高まります。
実質金利とドル高のダブルパンチがもたらした影響
テーパータントラムは、「実質金利上昇+ドル高」が金価格の下落要因となる典型例として、現在でも分析の対象となっています。(出典: kaitori-daikichi)
金価格が一時的に下落したものの、その後は上昇トレンドに復帰しています。
コロナショック(2020年):一時急落とその後の史上最高値更新
2020年2〜3月に発生したコロナショックは、世界的な株価暴落と景気急減速を引き起こしました。この局面でも、金相場は一時的な急落を経験しました。(出典: diamond)
再び発生した「換金売り」と、その後の急速な回復の違い
コロナショック時もリーマンショックと同様に、「全資産キャッシュ化」の動きで金も売られ、NY金は1,600ドル台から1,400ドル台に急落しました。(出典: gold.bullionvault)
しかし、リーマンショック期と決定的に異なったのは、各国が前例のない大規模金融緩和と財政出動を迅速に実施した点です。
大規模な金融緩和が「安全資産」としての金の価値を再認識させた
大規模な金融緩和の結果、2020年4月以降、金価格は急速に回復し、同年夏には2,000ドル超の史上最高値を更新する「V字回復+新高値」パターンとなりました。(出典: brandgarden)
専門家は、流動性危機局面では一時的に金も売られるが、その後の低金利・マネー供給増で金が最も長期的な受益者になりやすいと指摘しています。(出典: sbisec)

リーマンショックとコロナショックを比較すると、暴落の初動は似ていますが、その後の金融政策のスピードと規模が、金の回復軌道を大きく変えたことがわかります。金融当局の対応が、金の「安全資産」としての価値を再認識させたと言えるでしょう。
【予兆とサイン】チャートから暴落の底を見極める3つの視点
過去の暴落事例には、チャート上にいくつかの共通した予兆やサインが現れることがあります。ここでは、暴落の最終局面や底打ちの可能性を探るための3つの重要な分析視点を解説します。
視点1:「セリングクライマックス」とは?パニック売りの最終局面
セリングクライマックスとは、暴落局面の終盤でパニック的な売りが集中し、出来高急増と大陰線・長い下ヒゲを伴う「売りの最終局面」を指します。
多くの投資家が損切りや撤退を余儀なくされ、その結果として底打ち反発の起点となり得るとされる概念です。
なぜセリングクライマックスが底打ちのサインとなり得るのか
セリングクライマックスでは、相場に参加しているほぼ全ての売りたい人が売り尽くし、売り圧力が枯渇します。
その結果、わずかな買いが入るだけで価格が急騰しやすくなるため、底打ちの可能性が高いサインとして多くの投資家に意識されます。
チャート上の特徴(大陰線・長い下ヒゲ)
チャート上では、セリングクライマックスは以下のような特徴で現れることが多いです。
視点2:「出来高」の急増は相場転換のエネルギー
出来高とは、一定期間に取引が成立した数量のことです。暴落局面において、この出来高の動きは、相場転換のエネルギーを測る重要な指標となります。
なぜ暴落時に出来高が急増するのか?
暴落時に出来高が急増するのは、主に以下の要因が考えられます。
出来高のピークアウトが示す市場心理の変化
出来高が急増した後に、その出来高が減少(ピークアウト)し、価格が反転する動きが見られた場合、それは売り圧力が一巡し、買いが優勢に転じた可能性を示唆します。
コロナショック期の金先物・ETFでは、2020年3月の急落局面で取引高が急増し、その後価格が底打ち・反転する動きが見られたと報告されています。(出典: gold.bullionvault)

出来高の急増は重要なサインですが、「ダマシ」も多いです。出来高が急増した「後」の落ち着きを確認することが、より確実な判断に繋がります。
出来高は相場の「体温」であり、その変化は相場の本質的なエネルギーを示唆すると言えるでしょう。
視点3:過去の暴落前に現れた共通の予兆
過去の暴落事例には、チャートパターンやテクニカル指標に、ある種の「予兆」が現れることがあります。これらのサインを事前に察知することで、来るべき暴落に備えることが可能です。
テクニカル指標の警告サイン(ダイバージェンスなど)
例えば、金相場の下落要因を解説した記事でも触れた「ダイバージェンス」は、価格が上昇しているにもかかわらず、RSIやMACDといったオシレーター系のテクニカル指標が弱気を示唆する現象です。
これは、上昇トレンドの勢いが鈍化していることを示し、反転下落の予兆となることがあります。
金融市場全体のセンチメント悪化
金相場単独の動きだけでなく、株式市場や債券市場など、金融市場全体のセンチメントの悪化も重要な予兆となります。特に、市場全体のボラティリティの急上昇や、リスク回避の動きが強まる中で、金価格にも下落圧力がかかることがあります。
あわせて読みたい:具体的な下落シグナル
暴落の予兆として現れる「三尊天井」や「ダイバージェンス」といった具体的なテクニカル指標について、さらに深く知りたい方はこちらの記事がおすすめです。
→ 金相場はなぜ下がる?チャートに出る下落シグナルと経済要因を解説

【リスク管理編】次の金相場暴落に備えるための3つの鉄則
過去の教訓を学び、暴落のサインを理解した上で、最も重要なのが具体的なリスク管理です。ここでは、次の暴落が来たときに慌てて「狼狽売り」をしないための、3つの鉄則を紹介します。
鉄則1:機械的な損切りルール「逆指値注文」を徹底する
暴落時に感情的な判断で損失を拡大させないためには、機械的な損切りルールを設定しておくことが不可欠です。その代表的な方法が逆指値注文です。
なぜ感情的な判断は失敗を招くのか
人間は、損失を確定することに対して強い抵抗感を感じる傾向があります(プロスペクト理論)。暴落時には、「もう少し待てば回復するかもしれない」という期待や、「損を認めたくない」という感情から、損切りが遅れ、結果的に損失を拡大させてしまうことがよくあります。
損失を限定し、精神的な安定を保つ逆指値の活用法
逆指値注文(ストップロス)とは、あらかじめ「この価格まで下がったら自動的に売却する」という注文を出しておくことです。

損切りは痛みを伴いますが、それは投資の「必要経費」と捉えるべきだと感じます。この経費を払えないと、再起不能の致命傷を負う可能性があることを、過去の暴落事例が教えてくれていると言えるでしょう。
鉄則2:ポートフォリオ全体で考える「資産分散」の重要性
「金は安全資産」と言われますが、前述の通り、リーマンショックやコロナショックの初動では金も売られました。金だけに全資産を集中させるのは賢明な戦略とは言えません。
なぜ金だけに投資するのは危険なのか
金はインフレヘッジや有事の資産として魅力的ですが、単一の資産クラスに集中投資することは、その資産が大きく下落した場合にポートフォリオ全体が大打撃を受けるリスクを抱えます。また、金自体も短期的な価格変動リスクを抱えています。
株式や債券など、他の資産との組み合わせ方
暴落時に金が一時的に下落したとしても、他の資産が堅調であることで、ポートフォリオ全体のリスクを軽減できます。
鉄則3:Yahoo!ファイナンスで「長期チャート」を確認し、現在地を把握する
短期的な価格変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが暴落時の冷静な判断に繋がります。そのために有効なのが、Yahoo!ファイナンスなどのチャートツールを使った長期チャート分析です。
長期チャートで暴落の歴史と回復パターンを視覚的に理解する
Yahoo!ファイナンスでは、過去10年、20年、さらにはそれ以上の期間の金価格チャートを確認することができます。
現在の価格が歴史的に見て割高か割安かを判断するヒント
長期チャートを見ることで、現在の金価格が過去のレンジの中でどの位置にあるのか、歴史的に見て割高なのか、割安なのかを大まかに判断するヒントを得られます。これにより、感情的な「狼狽売り」や「飛びつき買い」を防ぎ、より客観的な視点で投資判断を下すことが可能になります。
金相場暴落に関するよくある質問(FAQ)
- QQ1: 過去の暴落と同じような下落はまた起こりますか?
- A
A1: はい、歴史が示すように、経済危機や金融政策の転換によって金相場の暴落は繰り返し起こる可能性があります。だからこそ、過去から学び、備えることが重要です。
- QQ2: 「換金売り」の時、金は安全資産ではないのですか?
- A
A2: 短期的には、他の資産と一緒に売られるため価格は下落します。しかし、その後の金融緩和局面などでは、インフレヘッジとしての価値が見直され、結果的に価格が上昇する傾向があるため、中長期的には安全資産としての役割を果たすと考えられています。
- QQ3: 暴落時に金をすべて売却すべきですか?
- A
A3: 一概には言えません。慌てて全てを売却する「狼狽売り」は、その後の回復局面を逃すことになり、多くの場合、後悔に繋がります。事前に決めたリスク管理のルールに従い、冷静に行動することが重要です。
- QQ4: 暴落は絶好の買い場になりますか?
- A
A4: 結果的に見れば買い場となることも多いですが、底打ちを見極めるのはプロでも困難です。時間分散を効かせて少しずつ買い下がるなど、リスクを管理した上での戦略が求められます。
▼次のステップ:日足分析で基礎を固める
過去の暴落からリスクを学んだ今こそ、足元の「日足チャート」を正しく読み解く基礎スキルを見直してみませんか?確実な分析力が身につきます。
→ 金相場の「日足」チャート分析入門|ローソク足と移動平均線の読み方

まとめ:過去の金相場暴落から学び、未来のリスクに備えよう
本記事では、金相場を襲った過去の主要な暴落事例を分析し、そこから得られる教訓と、将来のリスクに備えるための具体的な手法を解説しました。金相場の暴落は避けられないものですが、知識と準備があれば、それを乗り越え、あるいはチャンスに変えることも可能です。
金相場暴落の歴史と教訓【総復習】
- 過去の暴落事例: リーマンショック、テーパータントラム、コロナショックなど、過去の暴落にはそれぞれ特徴的な原因と値動きのパターンがあります。特に、金融危機時の「換金売り」と、その後の金融緩和による価格回復は重要な教訓です。
- 暴落の底打ちサイン: 暴落の最終局面では、「セリングクライマックス」や「出来高の急増」といったサインが見られることがあります。しかし、これらは「ダマシ」である可能性も常に考慮する必要があります。
- リスク管理の重要性: 過去の失敗の多くは、感情的な「狼狽売り」によるものです。これを防ぐためには、「逆指値注文」や「資産分散」、そして「長期的な視点」といったリスク管理の徹底が不可欠です。
次の一歩:あなたのリスク管理戦略を見直そう
この記事で学んだ知識は、金相場暴落という避けられない現象に対して、あなたが冷静に、そして戦略的に対応するための武器となります。ぜひ、ご自身の投資ポートフォリオとリスク管理戦略を見直し、次の市場変動に備えてください。

過去の暴落を知ることは、未来を正確に予測するためではなく、未知の事態に直面したときに冷静さを失わないための「備え」であるという見解です。知識が、感情に流されない強い投資家を育むと信じています。

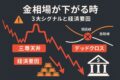
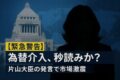
コメント